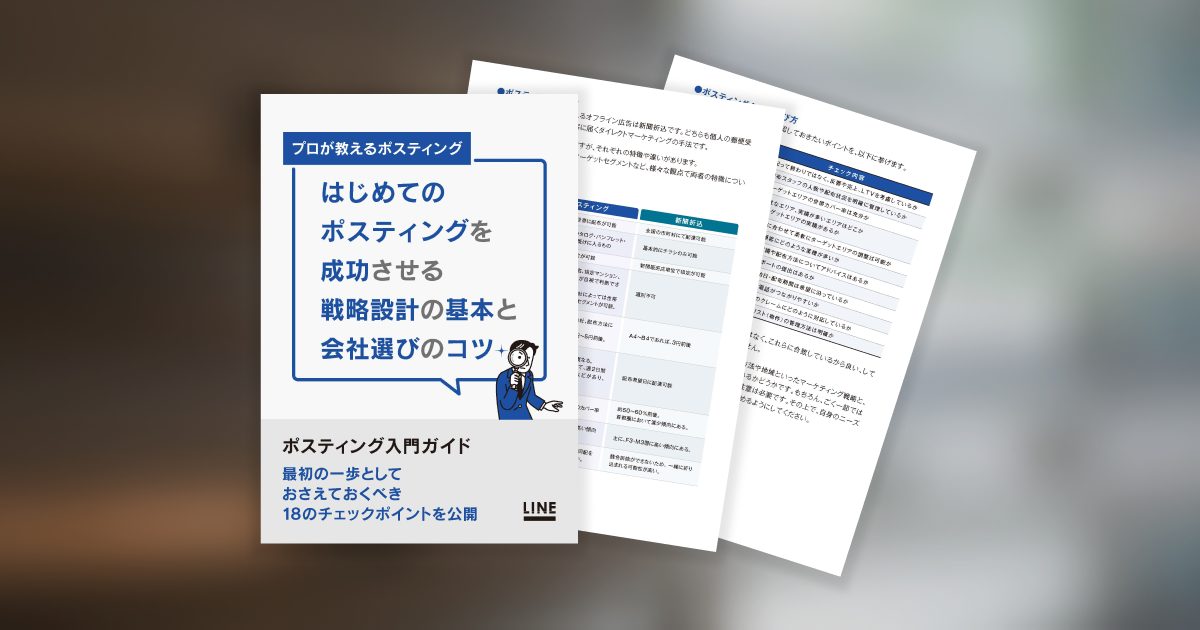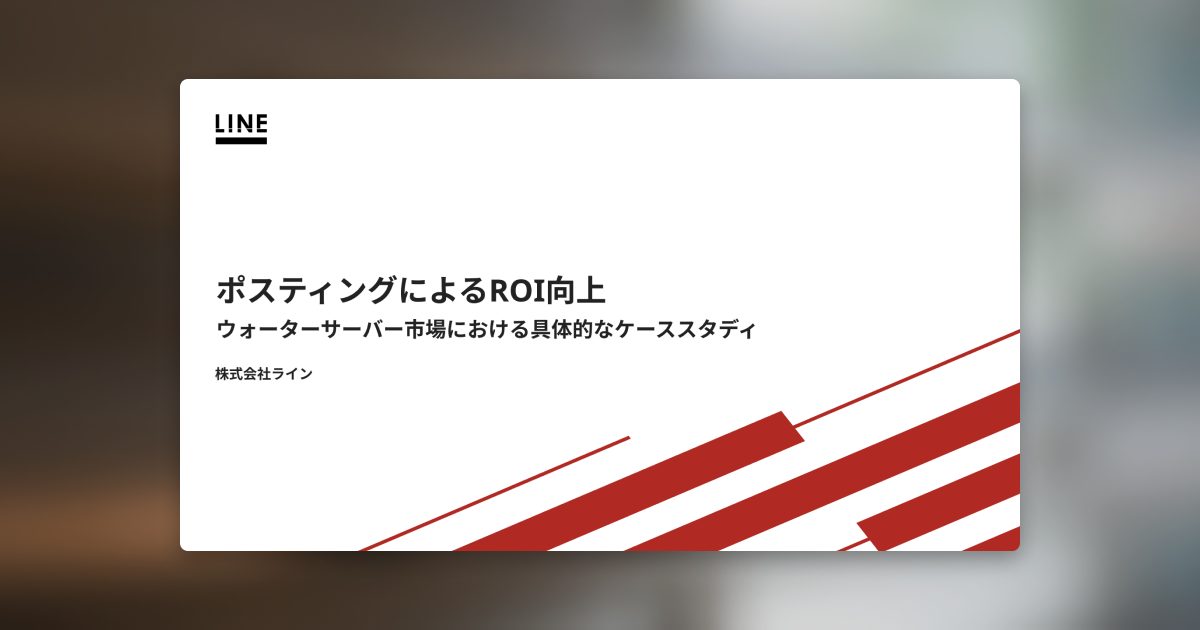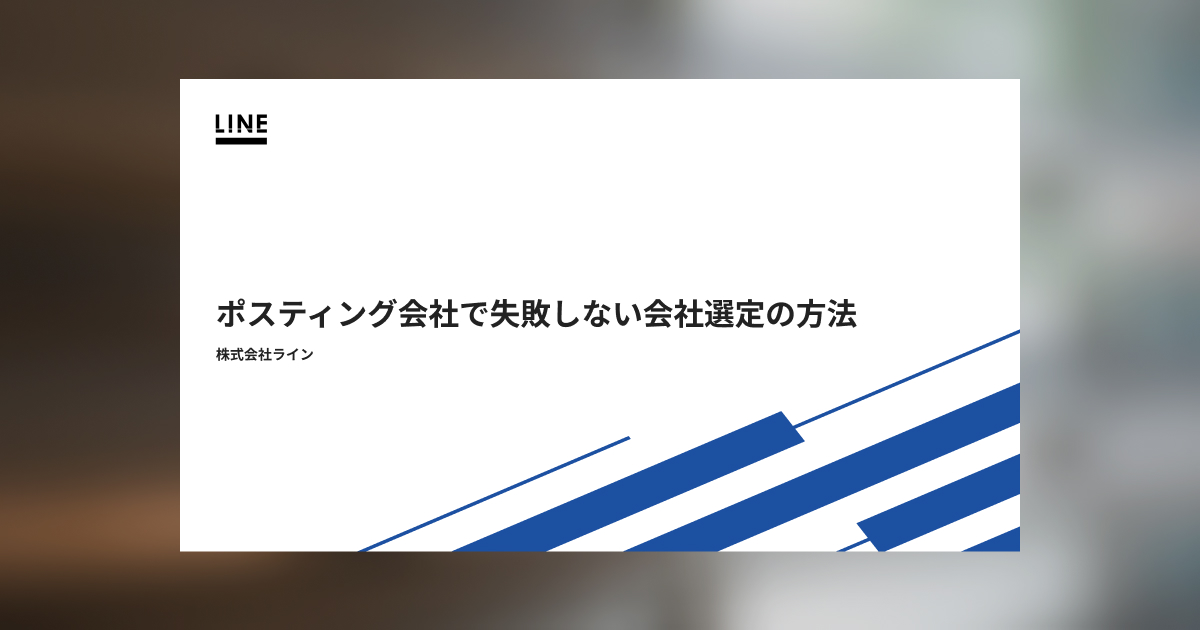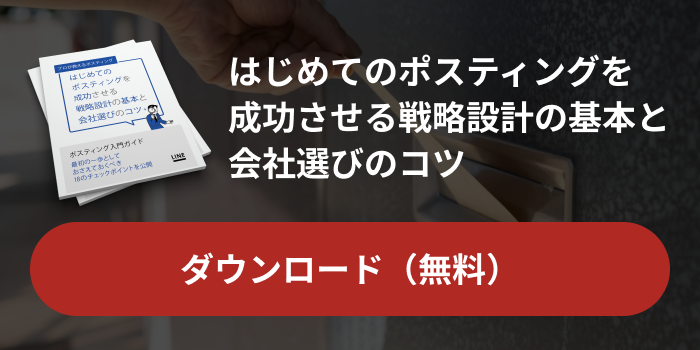見やすいチラシは何が違う?目を引くチラシの作り方やデザインのポイントを解説

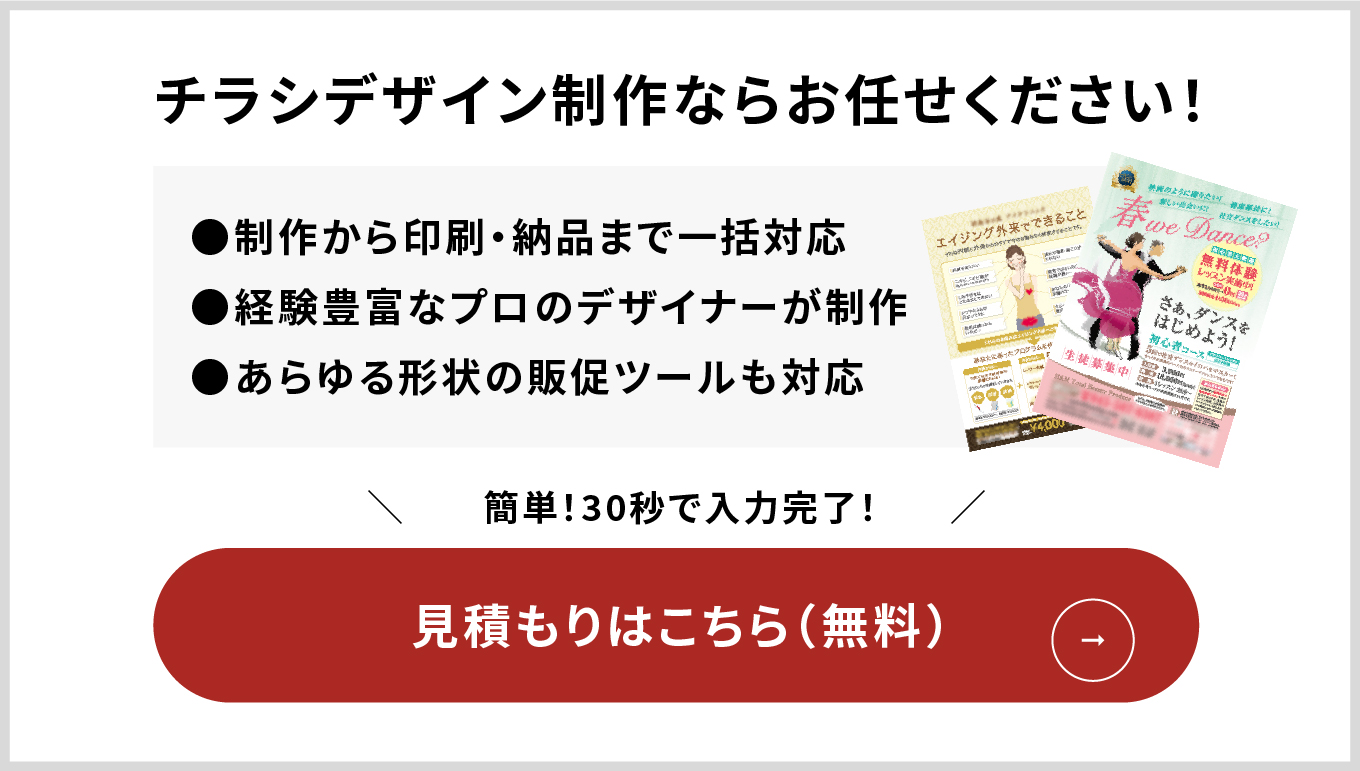
自分でチラシを作成したものの、見づらく仕上がってしまったり、伝えたい内容が多すぎて何を強調すべきか分からなくなってしまった、という経験はありませんか。
チラシは、見やすさや目を引くデザインの有無によって、その反響率が大きく変わります。見やすいチラシには共通する特徴があり、その作り方やデザインのポイントを理解すれば、初めての方でも反響率の高いチラシを作成できる可能性があります。
本記事では、見やすいチラシの特徴や重視すべき点、デザインのポイントについて詳しく解説します。この記事を参考に、よりターゲットの目を引くチラシ作りに役立ててみてください。
目次
目を引く見やすいチラシは何が違う?

目を引く見やすいチラシと、そうでないチラシの大きな違いは、以下の3つが挙げられます。
- キャッチコピーにインパクトがある
- 見やすいレイアウトになっている
- デザインで差別化を図っている
目を引く見やすいチラシにある特徴を理解し、自社のチラシに生かすことで反響率を高めることができます。反対に、自社のチラシが当てはまっていない場合は、期待する反響が得られない要因となっている可能性があるため、比較検証することをおすすめします。
キャッチコピーにインパクトがある
目を引くチラシの多くは、インパクトのあるキャッチコピーが特徴です。顧客は日々多くのチラシを受け取るため、すべてに目を通すことは難しいと考えられます。必要かどうかを判断するのは一瞬だと言われており、最初に目に入る言葉で「自分に必要だ」と感じてもらうことが重要です。
そのため、キャッチコピーには強い印象を与える工夫が求められます。具体的な数字を取り入れて信頼性を高めたり、クーポンや割引券などの特典を盛り込むのもおすすめです。
見やすいレイアウトになっている
目を引くチラシを作るためには、レイアウトの見やすさも欠かせないポイントです。レイアウトが整っていれば、情報がスムーズに伝わり、読む側もストレスなく内容を理解できます。
見やすいレイアウトにするコツは、情報をブロックごとに分けて整理することです。各ブロックにはタイトルを付け、内容を簡潔にまとめましょう。さらに、要素の位置やラインを揃えることで統一感が生まれ、より見やすいチラシになります。
デザインで差別化を図っている
目を引くチラシを作るためには、デザインで差別化を図ることも重要です。差別化ができていないと、他社のチラシに埋もれてしまい、目に留まらない可能性があります。
差別化の方法としては、目立つ色や印象的な画像を取り入れることがおすすめです。こうした要素はインパクトを与え、視線を引きやすくなります。ただし、過度に使いすぎると全体が見づらくなる恐れがあるため、バランスを意識することが大切です。
参考:「おもしろいチラシデザイン」で差をつける!革新的な広告の例
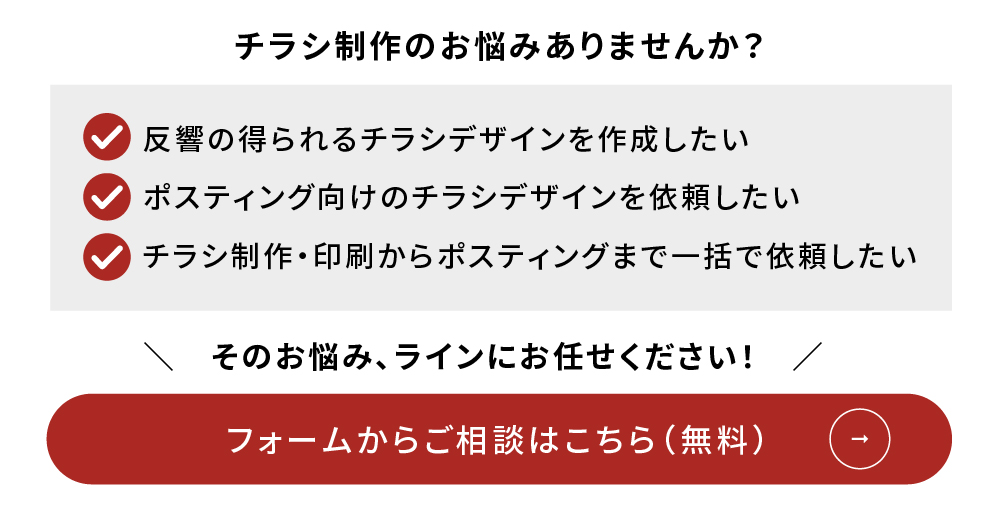
デザインの前に!見やすいチラシの「土台」を作る4ステップ

見やすく効果的なチラシを作るには、いきなりデザインから始めるのではなく、まずは情報設計の「土台」をしっかり整えることが大切です。
ここでは、チラシ作成の前に行っておきたい4つのステップをご紹介します。
- 訴求したいターゲットを明確にする
- キャッチコピーを考える
- 記載する情報を整理する
- 手書きでOK!レイアウトの「設計図」を描く
この準備段階を丁寧に行うことで、伝えたい情報がぶれず、デザインもスムーズに進められます。
ステップ1:訴求したいターゲットを明確にする
目を引く見やすいチラシにするために大切なことは、訴求したいターゲットを明確にすることです。ターゲットが明確になっていなければ、何を伝えたいのかがわかりづらいチラシになってしまうだけでなく、ターゲットの目を引くことができない可能性があります。
ターゲットを明確にする際には、年齢や性別、年収など、できるだけ具体的にイメージして、ペルソナを設定することがポイントです。家族構成やライフスタイルも分析することで、より情報を絞り込みやすくなります。
ターゲットが明確であればあるほど、ターゲットに合うチラシ作成が可能になるため、高い反響率が期待できます。
ステップ2:キャッチコピーを考える
目を引く見やすいチラシにするためには、キャッチコピーを考えることも大切です。キャッチコピーは、ターゲットの興味を引くためにも重要な要素となります。必ず見てほしい部分となるため、チラシの中でも特に大きく記載しましょう。
キャッチコピーを考える際には、他社との違いや自社にしかない強み、ターゲットが悩んでいることを記載するのがおすすめです。ただし、ターゲットによって記載すべき内容は異なるため、ターゲットの需要を理解したうえで、適切なキャッチコピーを作成しましょう。
ステップ3:記載する情報を整理する
目を引く見やすいチラシにするためには、記載する情報を整理することが大切です。チラシの中に情報が多すぎてしまうと、何が重要なのかがわからなくなってしまいます。また、読むこと自体にストレスを感じてしまう恐れもあるため注意が必要です。
まずは5W1H(誰に・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように)をもとに、「何を一番伝えたいのか」を明確にしましょう。そのうえで、記載する情報を以下の3つの視点で洗い出してみてください。
| 注目 | 目を引かせたい情報(例:割引、キャンペーン、特典) |
|---|---|
| 興味 | 詳細を知ってもらうための情報(例:商品内容、料金、実績) |
| 行動 | 問い合わせ・来店・予約などのアクションにつなげる情報 (例:連絡先、QRコード、地図) |
このように整理すると、情報の取捨選択がしやすくなり、チラシ全体の構成も見やすくなります。記載する情報は最低限に抑え、シンプルで見やすいチラシにすることを意識しましょう。
ステップ4:手書きでOK!レイアウトの「設計図」を描く
最後に、実際のデザイン作業に入る前に、レイアウトの設計図(ラフ)を描いてみましょう。「どこに何を配置するか」をあらかじめ決めておくことで、制作作業が格段にスムーズになります。
おすすめは、紙面を縦に3分割して「視線の流れ」を意識する方法です。人は左上から右下へと自然に視線を動かすため、
- 上部:キャッチコピーや目立たせたい要素
- 中央:詳細な情報や画像
- 下部:問い合わせ先や行動喚起(CTA)
といった配置にすると、見やすく、伝わりやすいチラシになります。
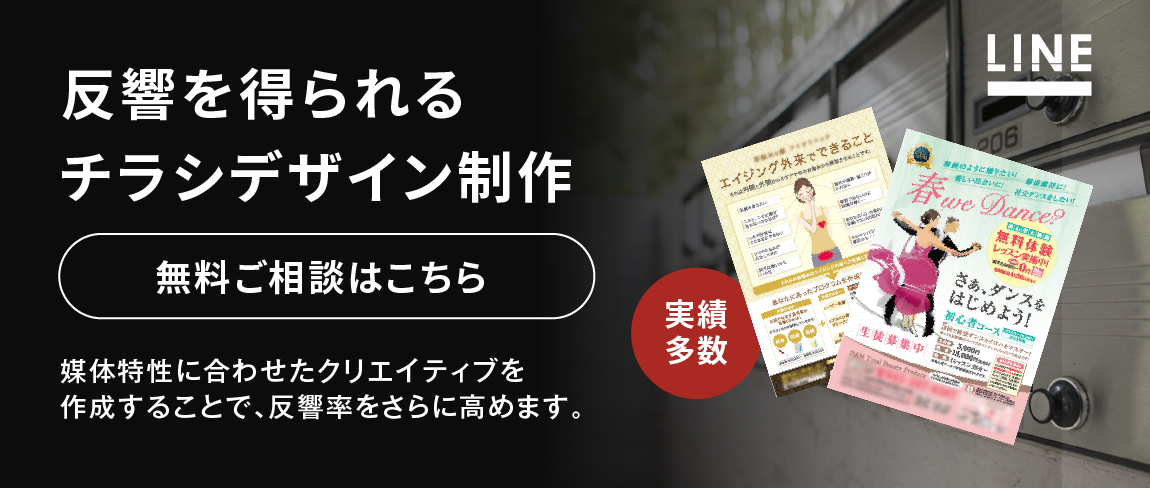
これだけは押さえたい!見やすいチラシ「3つの基本原則」

見やすいチラシを作るためには、「見やすさ」の基準を持っておくことが大切です。基準があることで、デザインや情報の整理がスムーズになり、判断もしやすくなります。ここでは、業種や目的に関係なく活用できる、チラシ作成における「見やすさの基本原則」を3つご紹介します。
- 原則1.情報をきちんと並べるだけで、見やすさは劇的に変わる
- 原則2.関連する情報は「グループ化」して見せる
- 原則3.「メリハリ」をつけて、一番見てほしい場所へ視線を誘導する
原則1.情報をきちんと並べるだけで、見やすさは劇的に変わる
「なんとなくゴチャゴチャして見える」というチラシの多くは、情報の整列ができていないことが原因です。要素をきちんと揃えるだけで、視線の流れがスムーズになり、チラシ全体に整った印象を与えることができます。
特に意識したいのが以下のポイントです。
| 文字や画像を左揃えにする | 視線が安定し、読みやすくなります。 |
|---|---|
| “見えない線”を意識して揃える | 項目の始まりや終わりのラインを揃えると、自然と 統一感が出ます。 |
| 余白の使い方をそろえる | 余白の大きさも「並べ方」の一部です。 |
こうした「整列」はデザインの基本であり、初心者でもすぐ実践できる重要なポイントです。
原則2.関連する情報は「グループ化」して見せる
情報が散らばって配置されていると、どれが関連する内容かが理解できず、読み手に負担をかけてしまう可能性があります。そこで活用したいのが「近接」の原則です。関連性のある情報をグループ化することで、内容が整理され、より見やすくなります。
具体的には、以下のような工夫が重要です。
| 項目ごとにまとまりを作る | 例:価格・商品名・説明をひとまとまりに |
|---|---|
| グループ間には適度な余白を設ける | 情報同士の境界が明確になり、読みやすさが アップします。 |
関連する情報であることが視覚的に伝わることで、チラシ全体の構成がより整理されます。
原則3.「メリハリ」をつけて、一番見てほしい場所へ視線を誘導する
ただ情報を並べるだけでは、読者の視線が定まらない恐れがあります。最も伝えたいポイントに視線を集めるには、「メリハリ(対比)」をつけることが重要です。
注目させたい要素には、以下のようなテクニックを活用しましょう。
| 色のコントラスト | 目立たせたい部分にだけ強い色を使う |
|---|---|
| サイズの対比 | 重要な言葉を大きく、それ以外は小さめに |
| 太字・囲みなどの装飾 | 目立つ形にすることで自然と注目される |
このように「対比」を意識することで、最初に読んでほしいキャッチコピーや、行動につなげたいボタン・QRコードなどにしっかりと視線を誘導できます。
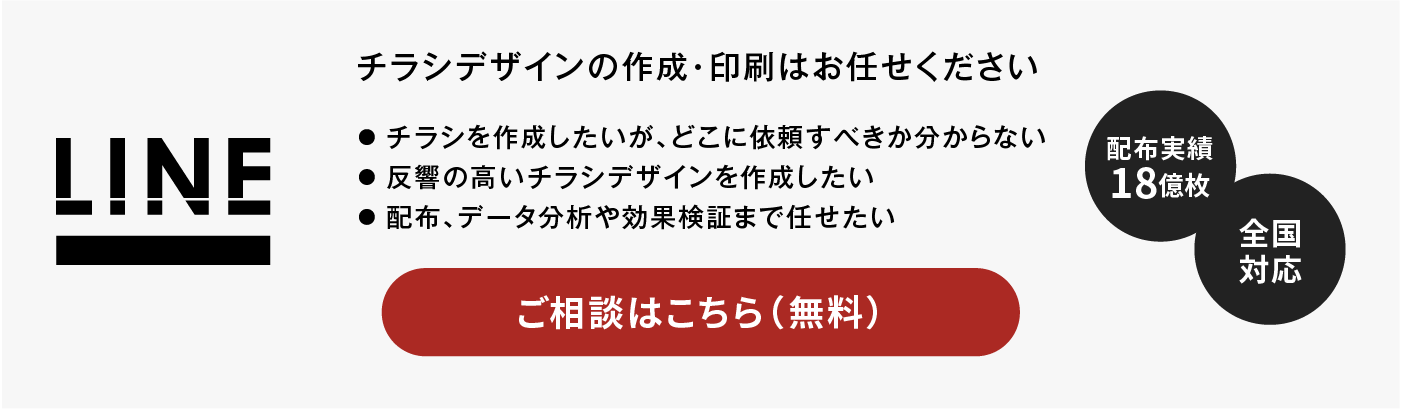
3つの原則を使った見やすいチラシデザイン10のコツ

ここでは、前章で紹介した3つの基本原則をもとに、実際のチラシづくりに活かせる10の具体的なテクニックをご紹介します。
- 視線の流れ「Z型」を意識して情報を配置する
- 「余白」を贅沢に使ってスッキリ見せる
- 情報を「枠」で囲って分かりやすく整理する
- 使うフォントは「2〜3種類まで」に絞り統一感を出す
- 重要な部分のフォントや色を強調する
- ターゲットやコンセプトに合った色を選ぶ
- 文字のジャンプ率を意識してメリハリをつける
- インパクトのある画像やイラストを活用する
- 数字を具体的に示す
- クーポンや割引券といった特典を付ける
上記は、特別なデザインスキルがなくても取り入れられる工夫です。ひとつひとつ意識することで、より見やすく、印象に残るチラシに近づきます。
1.視線の流れ「Z型」を意識して情報を配置する
人の視線は、Z型に動くという統計的な法則があります。特にチラシやバナー広告のように、一面で情報を伝えるレイアウトでは、この視線誘導を意識すると効果的が期待できます。
Zの法則:左上 → 右上 → 左下 → 右下と、Zの形に視線が流れる
このように、レイアウトに合わせた視線誘導を意識することで、情報を自然な順序で読んでもらいやすくなり、伝えたい内容がしっかり届けられるチラシになります。
2.「余白」を贅沢に使ってスッキリ見せる
見やすいチラシに共通する特徴のひとつが「余白の使い方」です。文字や写真を詰め込みすぎると、視線がどこに向かえばよいか分からず、読み手を疲れさせてしまう恐れがあります。
紙の端には5ミリから1センチ程度の余白を確保し、情報と情報の間にも間隔を持たせることで、全体の印象がすっきりとし、伝えたい内容が引き立ちます。
「空白=無駄」と考えず、余白を“見せるデザイン”として活用することで、より洗練された印象のチラシに仕上がります。
3.情報を「枠」で囲って分かりやすく整理する
情報量の多いチラシでは、内容がきちんと整理されていることが、見やすさに大きく影響します。どこに何が書かれているのかが一目でわかるレイアウトを意識することで、読み手のストレスを減らし、伝えたい情報がよりスムーズに届くようになります。
そこで有効なのが、関連する情報を「枠」で囲むという方法です。商品の説明やキャンペーン情報など、内容ごとにグルーピングして枠でまとめることで、それぞれの情報が整理され、視覚的にも分かりやすくなります。加えて、枠を使うことで自然と余白が生まれ、チラシ全体にメリハリが出るという効果もあります。
ただし、すべての要素を細かく囲ってしまうと、かえって窮屈で読みづらいレイアウトになってしまうこともあります。情報を分類する「大枠」を活用し、重要な情報だけを囲うことで、整理と視認性のバランスが取れたデザインになります。読み手の目線の動きや、伝えたい優先順位を意識しながら、適度な枠使いを心がけることがポイントです。
4.使うフォントは「2〜3種類まで」に絞り統一感を出す
チラシを落ち着いた印象に仕上げるには、フォントの使い方も重要です。フォントの種類を増やしすぎると、全体的に読みづらい印象になってしまう恐れがあります。タイトル用、本文用、強調用の3種類程度に抑えると、全体の統一感が保たれ、情報の伝達もスムーズになります。
さらに、色使いもフォントと同じく2~3色程度に絞ることで、まとまりのある見やすいチラシに仕上がります。
5.重要な部分のフォントや色を強調する
チラシの中で最も伝えたい情報が、他の情報に埋もれてしまっては意味がありません。そこで意識したいのが、フォントや色による強調です。たとえば「50%OFF」「本日限り」などの訴求ポイントは、文字を大きくしたり、目立つ色を使ったりすることで視線を集めることができます。
また、フォントの種類によっても、読み手に与える印象は大きく変わります。力強さや親しみを伝えたいときにはゴシック体が効果的で、上品さや信頼感を演出したい場合は明朝体を使うのがおすすめです。こうした要素を上手に組み合わせることで、「ここを見てほしい」という意図が伝わりやすくなり、チラシ全体の訴求力も高まります。
6.ターゲットやコンセプトに合った色を選ぶ
配色はチラシ全体の印象を左右する大きな要素です。ターゲット層や商材のイメージに合った色を選ぶことで、親しみやすさや信頼感につながります。
たとえば、男性向けであれば力強い色合いや太字のゴシック体、女性向けであれば柔らかいパステルカラーや手書き風フォントが効果を期待できます。
また、ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの割合を7:2.5:0.5にすると、バランスよくまとまります。
7.文字のジャンプ率を意識してメリハリをつける
ジャンプ率とは、見出しと本文の文字サイズの差を示す用語です。この差を活かすことで、読みやすく視覚的にメリハリのあるデザインが期待できます。
たとえば、ジャンプ率が高いと、若々しく勢いのある印象になり、イベントやセール情報などのチラシにも適しています。一方、ジャンプ率が低めだと落ち着いた印象になり、信頼感や高級感を伝える業種や商材に向いている傾向があります。
8.インパクトのある画像やイラストを活用する
目を引く見やすいチラシデザインを作成するには、文字だけではなく、印象に残る画像やイラストを活用するのもおすすめです。
商品の使用シーンやサービスの内容が一目でわかる画像やイラストを使うことで、内容の理解を深める効果だけでなく、読み手の注意を引きつけることも可能です。また、視線を集めたい部分に画像やイラストを配置することで、全体の構成にもリズムが生まれます。
9.数字を具体的に示す
「お得」や「人気」といったあいまいな言葉よりも、「50%OFF」「累計1,000件以上」などの具体的な数字を使った表現のほうが、目を引きやすく、説得力も高まります。数字には客観性があるため、読み手に安心感や信頼感を与える効果が期待できます。
また、数字を載せるだけでなく、「その情報の根拠」を明記することも重要です。たとえば「お客様満足度98%」と書く場合には、「2024年4月 自社アンケート調査より」など、出典や調査内容を補足することで、情報の信ぴょう性が高まります。
10.クーポンや割引券といった特典を付ける
チラシを見た人に「行動してもらう」きっかけとして、特典を用意するのは有効です。チラシに特典が付いているだけでも、読み手の目を引きやすくなります。
たとえば、「このチラシ持参で10%OFF」「先着20名様にプレゼント」といった特典を設けることで、手に取った人の来店や問い合わせを促しやすくなります。
また、クーポンや割引券の特典を付けておくことで、チラシの保存率も高まる可能性があります。チラシを保存してもらえれば、長期的な売り上げに繋がることも期待できます。
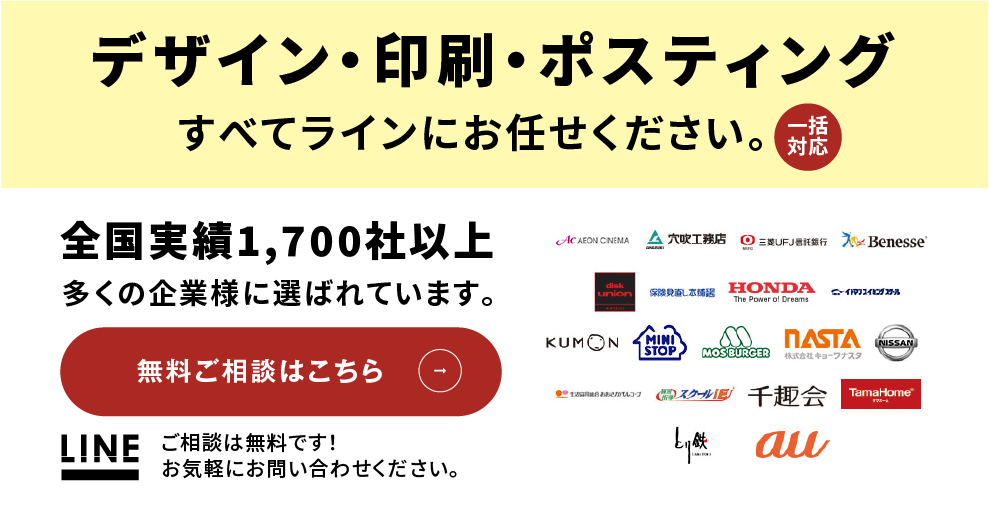
目を引く見やすいチラシ作成は株式会社ラインがおすすめ

チラシは、ただ情報を詰め込むだけでは伝わりません。大切なのは、「誰に」「何を届けたいのか」をはっきりさせたうえで、情報を整理し、見やすくわかりやすい形でデザインすることです。
本記事で紹介した「整列」「グループ化」「メリハリ」の3つの原則と、それを具体化する10のコツを意識することで、チラシの印象は大きく変わる可能性があります。
フォントや配色、余白の使い方、視線の流れなど、ちょっとした工夫が、読み手の理解や行動を促すきっかけになります。専門的なデザインスキルがなくても、ポイントを押さえることでより効果的なチラシを作ることができますので、ぜひ今回の内容を参考に、見やすいチラシの作成に役立ててみてください。
目を引く見やすいチラシ作成を依頼したい場合は、株式会社ラインへご相談ください。株式会社ラインでは、過去の実績を生かしたチラシ作成はもちろん、媒体のご提案から手配、効果検証まですべてお任せいただけます。初めてチラシの作成を検討している場合でも、一から丁寧にご説明させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
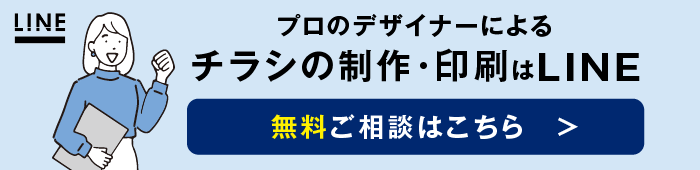
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 26年02月04日
26年02月04日