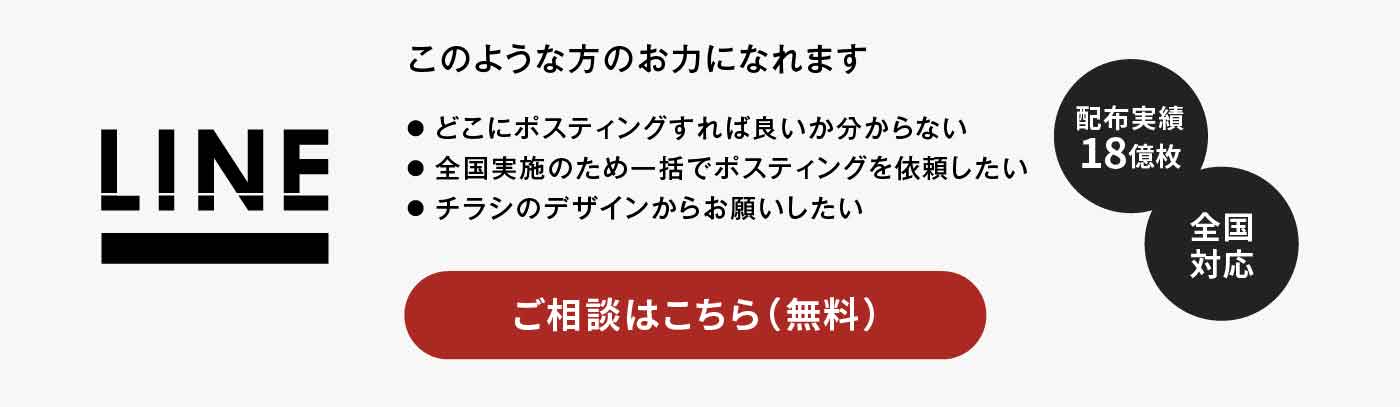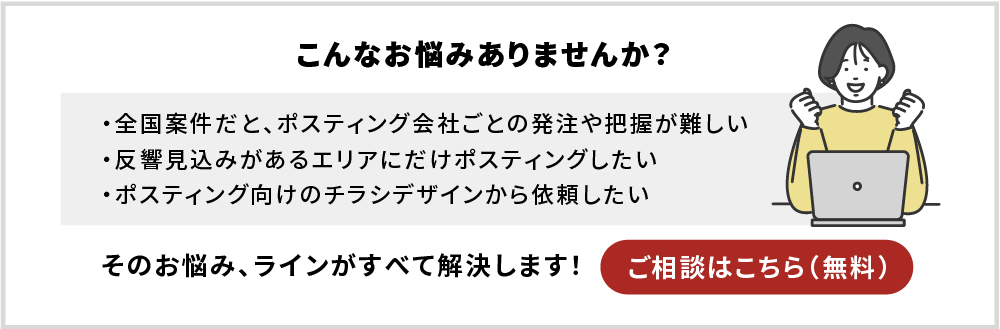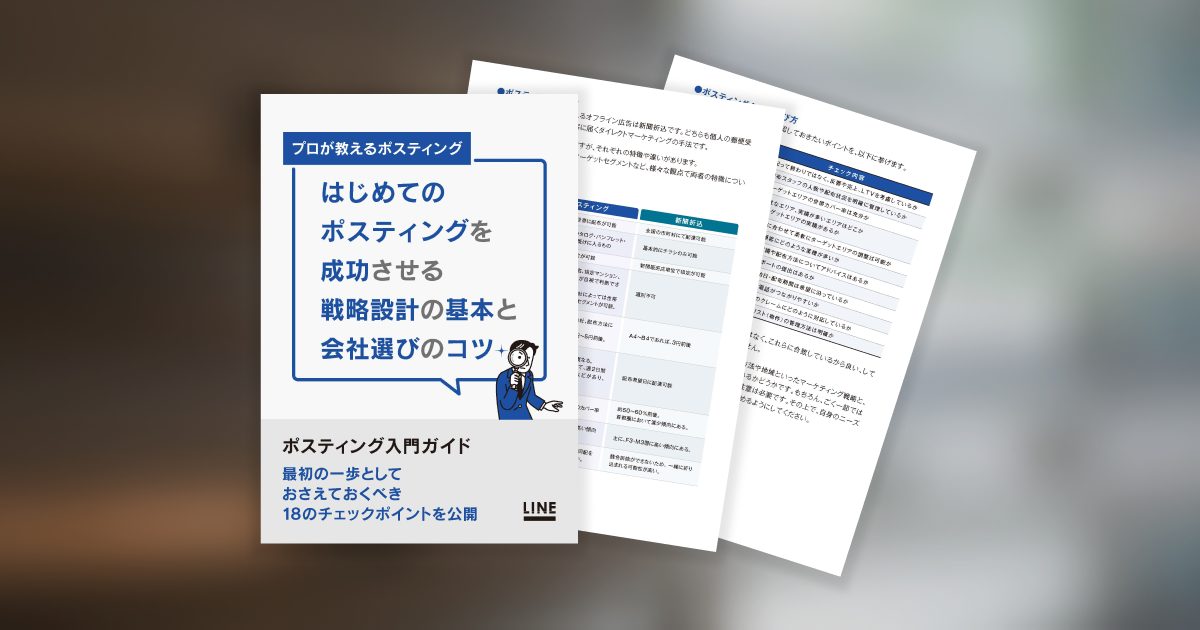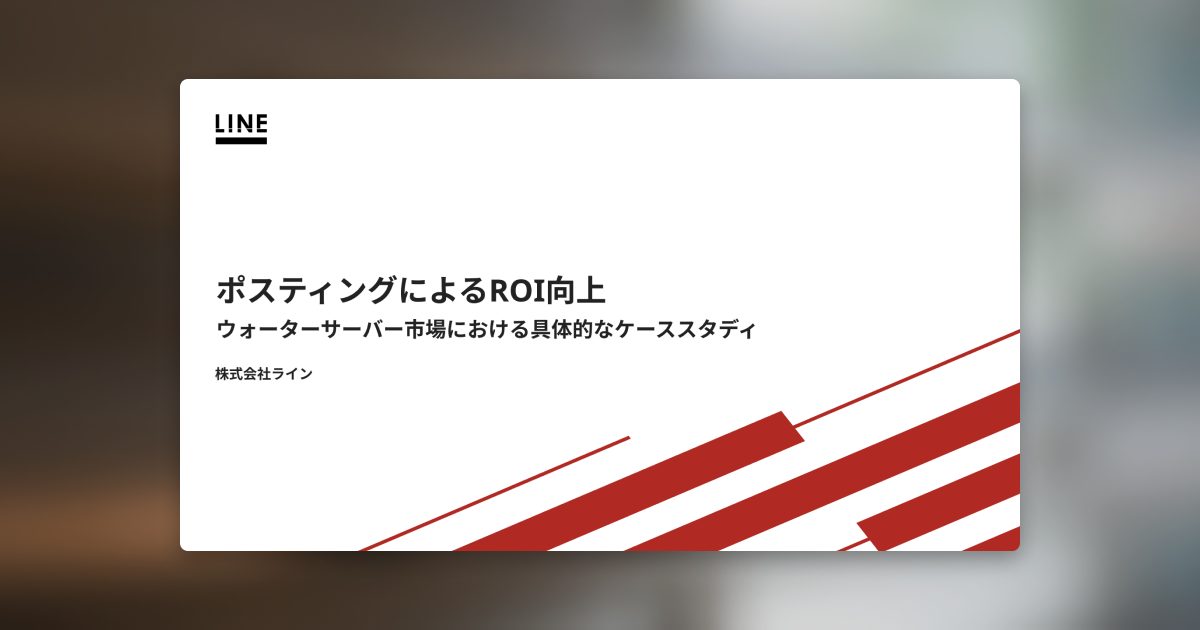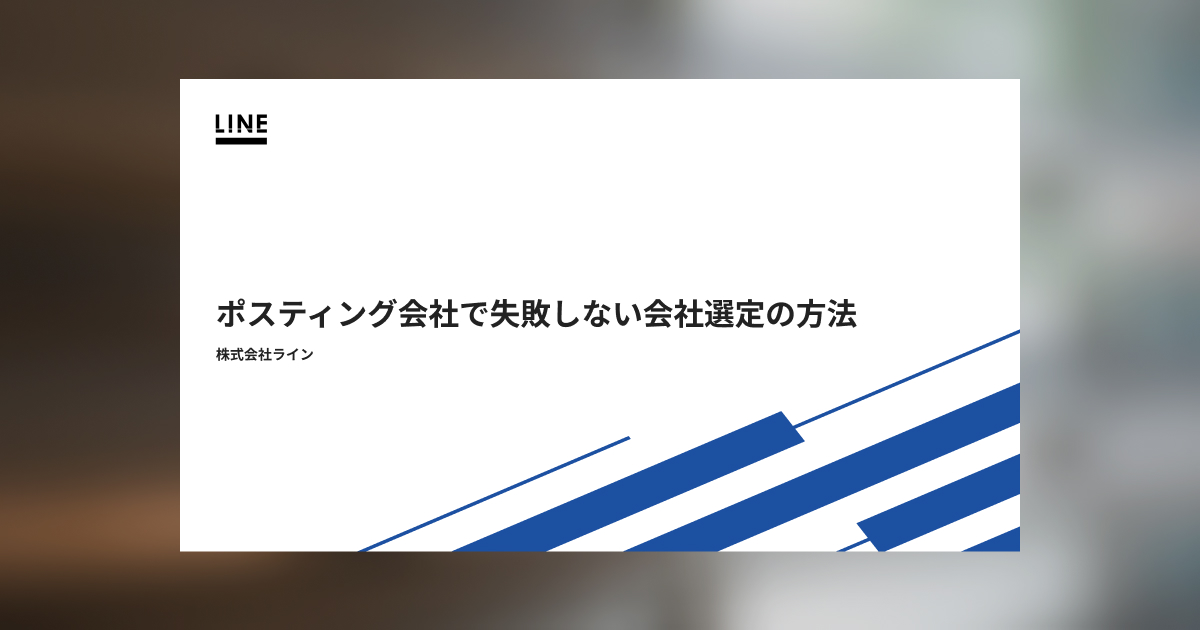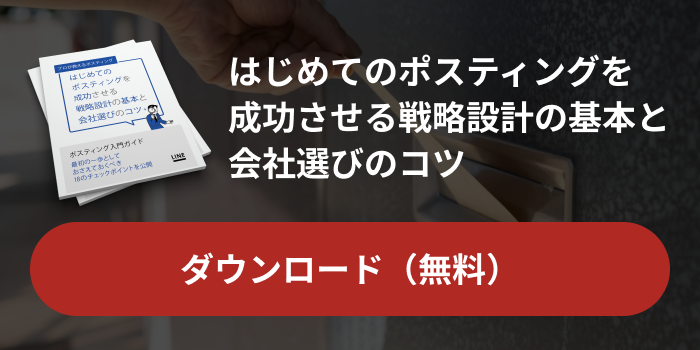ポスティングは法律違反?違法となるケースや対処法・トラブルの予防策も解説
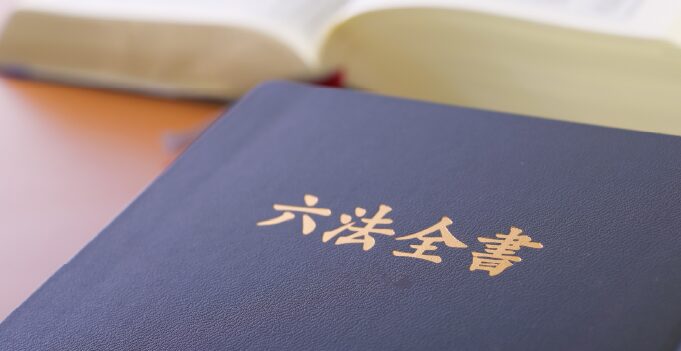

ポスティングは、チラシやパンフレットなどの広告物を直接郵便受けに届けられる宣伝手法ですが、配布方法を誤ると法律上の問題につながったり、ごく僅かですが住民との間でトラブルに発展してしまう可能性もあるため注意が必要です。こうした背景から、「ポスティングは法律違反になるのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
本記事では、ポスティングが違法となるケースやその対処法、さらにトラブルを未然に防ぐ予防策について詳しく解説します。トラブルを避けて集客を成功させるためにも、どのような場合にポスティングが違法になるのかを、正しく理解しておきましょう。
目次
ポスティング人気エリア
\ポスティングを実施したいと思ったら /
「ポスティングをしたいけど、何から始めれば良いか分からない」という方は、ぜひ株式会社ラインにご相談ください。
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、すべての業務をお任せいただけます。
法律上ポスティングは違法になるのか

結論から申し上げますと、ポスティング自体は法律上違法とされているわけではありません。ただし、配布の方法や運営の仕方によっては、法律に抵触する可能性が生じる点に注意が必要です。
具体的には、違法となる直接的な原因は「ポスティング」という行為そのものではなく、ポスティングを行う際の行動や対応に関係しています。そのため、ポスティングを外部の業者へ依頼する際には、どのような配布方法で運営しているのかをしっかり確認することが大切です。
誠実に活動している業者の多くは、地域のルールや住民への配慮を徹底し、トラブルにならないよう注意を払って配布を行っています。しかし、配布方法や運営のスタイルによっては、思わぬクレームにつながるケースもあるため、信頼できる業者選びと事前確認が重要といえます。
– 関連記事 –

ポスティングが法律上違法になるケース

ポスティングは基本的に合法ですが、配布方法によっては法律に抵触する可能性があります。
代表的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 敷地内に無断で入る(住居侵入罪)
- ポスティング禁止の表示がある場所への配布(軽犯罪法)
- 一度投函したチラシを取り出す(軽犯罪法)
- 公序良俗に反するチラシを配布(風俗営業法)
- 信書に該当する文書をポスティングする(郵便法)
これらを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎながら、より効果的なポスティングを実現できます。
敷地内に無断で入る(住居侵入罪)
住居や管理された敷地内に正当な理由なく立ち入ると、刑法第130条(住居侵入罪)に該当する可能性があります。
| 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 (引用元:刑法第130条) |
郵便受けが住宅の敷地内にある場合や、マンションなどオートロック付きの建物に無断で入ることは、この条文に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
ポスティング禁止の表示がある場所への配布(軽犯罪法)
「チラシ投函お断り」や「ポスティング禁止」などの表示がある場合、配布を行うと軽犯罪法第一条三十二号に該当する恐れがあります。
| 軽犯罪法第一条三十二号 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 |
住民の意思表示が明確にされている場合は、トラブル回避のためにも配布は控えることが望ましいでしょう。
一度投函したチラシを取り出す(軽犯罪法)
すでに投函したチラシを取り出す行為も、軽犯罪法第一条三十二号に抵触する可能性があります。配布した広告物は住民の所有物となるため、投函する住宅を間違えたなどの理由で、すでに投函したチラシを勝手に取り出すことは控えましょう。
公序良俗に反するチラシを配布(風俗営業法)
風俗関連の広告や公序良俗に反する内容を含むチラシの配布は、風俗営業法(第二十八条第5項)により禁止されています。
| 風俗営業法第二十八条第5項 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。〜ビラ等を頒布すること。 |
また、都道府県の迷惑条例法に触れる可能性もありますので、不適切な広告のポスティングはしないように徹底しましょう。
信書に該当する文書をポスティングする(郵便法)
郵便法では、特定の受取人に宛てた信書を日本郵便以外が送達することを禁止しています。
| 郵便法第四条2項 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 |
「○○様」「△△株式会社御中」といった特定の宛名を記載した文書を直接投函する行為は郵便法違反にあたる可能性があります。
一方で、チラシ・フリーペーパー・イベント案内など、不特定多数を対象とする広告物は信書に該当しません。したがって、一般的なポスティング広告は問題ありませんが、特定宛名入りの文書は避ける必要があります。
ポスティングでやってはいけないこと

法律上違法とならない場合でも、ポスティングは稀にトラブルやクレームにつながるケースがあります。できるだけトラブルに発展しないよう、以下の避けるべき点を意識することをおすすめします。
- 「ポスティング禁止」の表示を無視する
- 共有部にチラシを散乱させる
- 一度に大量のチラシを詰め込む
- 早朝や深夜に配布を行う
- 敷地内に駐車する
これらの点に気を配ることで、より安全かつ円滑にポスティングを進められます。
「ポスティング禁止」の表示を無視する
「チラシ投函お断り」などの表示がある場所にポスティングを行うことは、居住者の意思を無視する行為です。法律的にも問題が発生する可能性があるうえ、トラブルやクレームの原因となるため、必ず表示を守るようにしましょう。
共有部にチラシを散乱させる
共用部にチラシが落ちていると、住民に不快感を与え、クレームにつながることがあります。わざとではなくても、ポスティングの際にきちんと差し込めていないと床に落ちてしまう可能性があります。
そのため、配布時にはポストの奥まで確実に入れたかどうかを確認することが重要になります。
一度に大量のチラシを詰め込む
郵便受けに大量のチラシを無理に押し込むと、郵便物を破損させたり、ポストを塞いでしまう原因となります。郵便受けの容量に配慮し、適量を配布することが大切です。
早朝や深夜に配布を行う
法律で時間帯が制限されているわけではありませんが、20時〜翌6時の配布は住民に不信感を与える可能性が高いといわれています。
住民に不快感を与えると、自社のイメージ低下や集客効果の低下にもつながる可能性があります。不審者に間違われるリスクもあるため、避けた方が良い時間帯であると考えられます。
– 関連記事 –
敷地内に駐車する
ポスティング時に車やバイクを停める場所を誤ると、法的なトラブルにつながる可能性があります。個人宅の庭先やマンションの駐車場は居住者の管理下にあるため、許可なく利用すれば「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われる恐れがあります。
「侵入」とは建物内に入り込むことだけでなく、管理権者の意思に反して敷地を利用する行為も含まれるため、短時間であっても注意が必要です。特に集合住宅の駐車場や共用スペースは誤解されやすく、「勝手に使用した」と受け取られれば通報に発展しかねません。
自社でポスティングを行う場合は、事前に公道上で一時的に停車可能な場所や、近隣の有料駐車場・駐輪場を確認しておくと安心です。
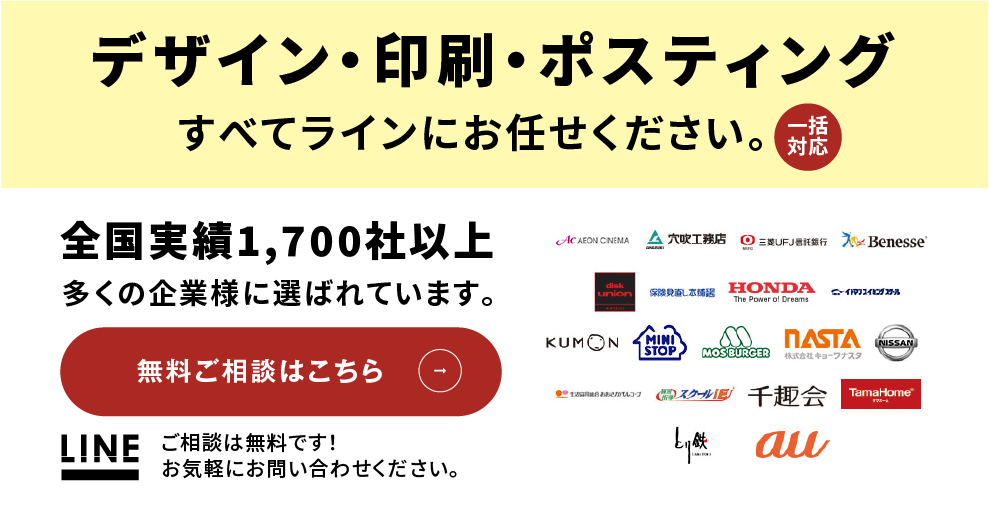
ポスティングでクレームが起きた際の対処法

万が一ポスティングでクレームが発生してしまった場合には、適切な対応を行うことで信頼回復につなげることができます。
主な対処法としては、以下の5つが挙げられます。
- 迅速な対応と謝罪をする
- チラシを回収する
- 問題点を確認する
- 再発防止策を提示する
- 理不尽な要求は慎重に判断する
これらを意識することで、誠実な姿勢を示しつつ、トラブルを最小限に抑えることが可能になります。
迅速な対応と謝罪をする
クレームが発生した際には、まず迅速に対応し、誠意を持って謝罪することが大切です。不快感や迷惑をかけた相手の気持ちを真摯に受け止め、落ち着いた態度で接することが信頼回復につながります。
また、ポスティング会社に依頼している場合でも、チラシに記載された自社の連絡先に問い合わせが入るケースがあります。その場合は、まず自社が誠意を持って対応した上で、速やかにポスティング会社に連絡し、適切な対応を依頼しましょう。
チラシを回収する
クレームが寄せられた際には、相手任せにせず、自ら配布先に出向いてチラシを回収する姿勢を示すことが大切です。処分を相手に委ねてしまうと「責任を取っていない」と受け止められる可能性があり、トラブルが長引く恐れもあります。
現地を訪問し直接謝罪した上でチラシを回収しましょう。すでに破棄されていた場合には無理に求めず、「処分していただきありがとうございます」という感謝を伝えることで誠意が伝わります。重要なのは印刷物の回収そのものではなく、誠実な対応を示す姿勢です。
問題点を確認する
クレームが発生した場合は、どのような状況で問題が起きたのかを具体的に確認することが大切です。
例えば「配布時間が早朝や深夜だった」「ポスティング禁止エリアに投函してしまった」など、原因を特定することで次回の改善につなげられます。原因を正しく把握する姿勢は、相手に誠意を伝える上でも重要です。
再発防止策を提示する
再度同様のトラブルが起きないよう、具体的な再発防止策を提示しましょう。謝罪だけでなく具体的な対策を提示することで、より信頼関係を回復しやすくなります。
たとえば、「ポスティング禁止」と表示されている住宅に誤って配布してしまった場合には、再度投函しないよう徹底する必要があります。
また、ポスティング会社に依頼している場合は、今後の配布リストから必ず除外するよう依頼内容を共有し、同様のミスを繰り返さないようにしましょう。
理不尽な要求は慎重に判断する
クレームの中には、「金銭や品物による補償」を求められるケースもあります。まずは事実関係を冷静に確認し、必要な対応と過剰な要求を区別することが重要です。
過度な補償に安易に応じてしまうと、新たなトラブルや継続的な要求につながる可能性があります。特に金銭が絡む場合は、必ず社内で共有・相談してから判断しましょう。
常識の範囲を超える要求や、謝罪だけでは解決が難しいケースでは、弁護士や専門機関に仲介を依頼することで冷静かつ公正に対応できます。
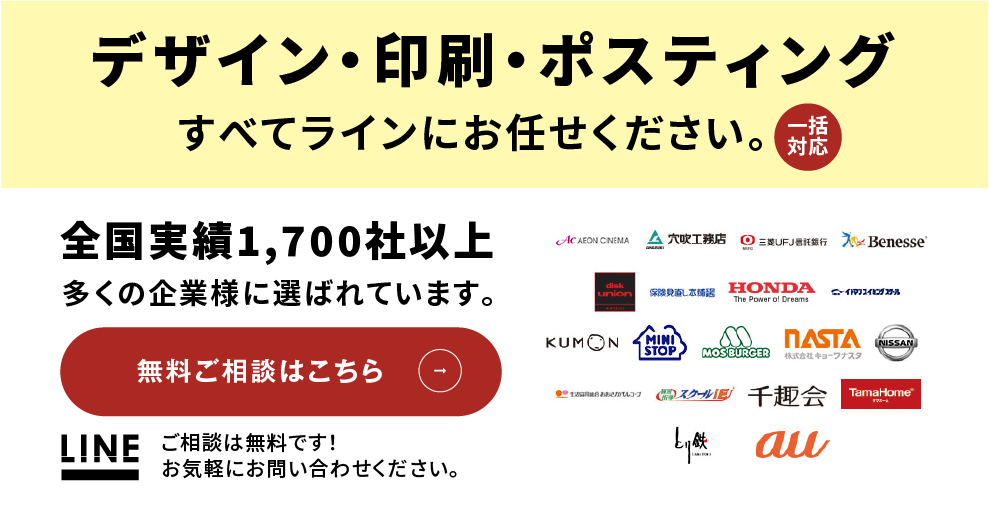
ポスティングでトラブルを防ぐための注意点

ポスティングは効果的な集客手段ですが、方法を誤るとトラブルにつながる可能性があります。ここでは、トラブルを未然に防ぐための注意点を解説します。
主な注意点の一例としては、以下の4つが挙げられます。
- チラシの内容を精査する
- 投函するエリアの事前調査を行う
- 配布禁止エリアをリストアップする
- 信頼できるポスティング会社に依頼する
事前に配慮を重ねることで、集客効果を高めつつ、より安心して取り組める環境を整えられます。
チラシの内容を精査する
ポスティングで使用するチラシは、内容が原因でクレームを招くリスクもあるため、事前に精査することが重要です。
特にチェックしておきたいポイントは以下のとおりです。
- キャッチコピーや画像が不快感を与えたり、社会的に不適切と受け止められる表現になっていないかを確認する
- 数字や実績を打ち出す場合には、裏付けや条件を明記し、誤解を与える誇張表現を避ける
- 価格や割引の条件は小さな文字に隠さず、誰にでも分かるように表示する
- 使用する写真やイラスト、地図、ロゴについて著作権や肖像権に問題がないかを必ずチェックする
- 地域性やターゲット層の文化的背景に配慮し、差別的・排他的に受け取られる可能性のある表現を避ける
また、トラブルを未然に防ぐためには、配布停止や問い合わせ窓口を明記しておき、連絡が来た際にスムーズに対応できる体制を整えることも有効です。
投函するエリアの事前調査を行う
ポスティングを行う前には、投函するエリアのルールや禁止表示を事前に確認しておくことが重要です。たとえば、「ポスティング禁止」と掲示された建物や、管理組合の規約によって特定ジャンルの配布が制限されているケースもあります。
また、過去にクレームが多かった地域や、投函禁止の張り紙が目立つエリアでは、特に慎重な調査が必要です。
調査で得られた情報は地図や社内ツールに反映させ、スタッフが現場で判断しやすい環境を整えておくと効果的です。さらに、こうした調査内容はスタッフ教育やオリエンテーションでも活用できるため、現場全体に判断基準を浸透させることにも役立ちます。
配布禁止エリアをリストアップする
事前調査やクレーム対応で判明した配布禁止先は、必ず記録として残しておきましょう。住所や建物名を正確に記録し、既存のデータを更新していけば、再投函を防ぎつつ効率的な配布につなげられます。
禁止リストはクレームを未然に防ぐだけでなく、「きちんと対応している会社」という信頼性の向上にも役立ちます。
さらに、ポスティング会社によっては独自の禁止リストを持っている場合もあるため、それを活用できるかを確認の上、自社のリストと照合することも効果的です。禁止リストの更新と運用を徹底することで、トラブルを防ぎながら効率的な配布を実現できます。
信頼できるポスティング会社に依頼する
ポスティングは、どの業者に依頼するかによっても成果が大きく変わる可能性があります。単価の安さだけで選んでしまうと、配布ルールが守られなかったり、クレーム対応が不十分なまま放置されるリスクがあります。
一方で、価格が高いからといって必ずしも安心できるわけではなく、下請けや孫請けに再委託されて管理が行き届かないケースもあるため注意が必要です。
信頼できる業者を見極めるためには、配布スタッフの教育体制や研修の有無、禁止エリアやクレーム発生時の対応ルールが明確に定められているかどうかを確認すると安心です。
また、過去のトラブル対応実績やクレーム窓口の有無も大切な判断材料になります。配布品質を安定させるためには、管理体制が透明で信頼できるポスティング会社に依頼することが重要です。
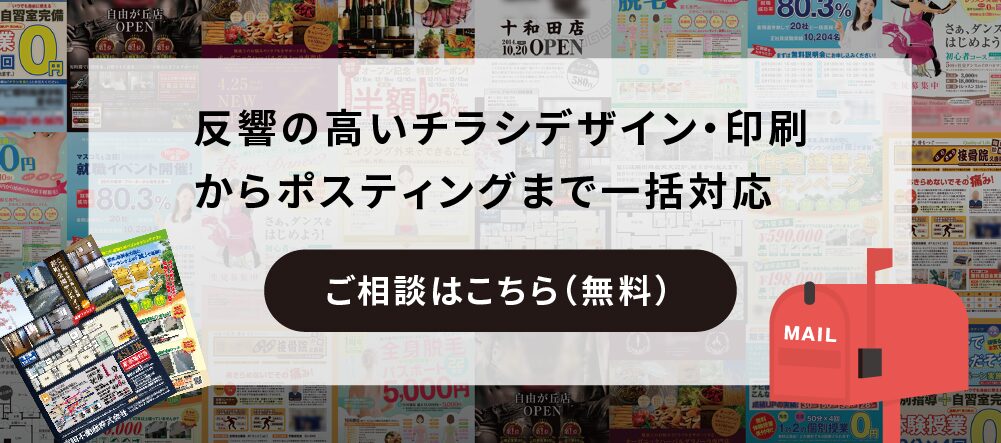
ラインは法律を守った優良ポスティング会社

ポスティングは効果的な集客方法である一方で、配布方法を誤れば法律違反やトラブルにつながる可能性があるため、正しい知識と慎重な対応が欠かせません。違法性はないとはいえ、安心して実施するためには、法律を順守し、住民への配慮を徹底することが重要です。
株式会社ラインでは、これまでの豊富な実績をもとに全国の投函禁止リストを保有しており、過去にクレームが発生した物件へのポスティングは行わないように徹底しています。
さらに、万が一クレームが発生した場合でも、謝罪、引取り等迅速かつ誠実にに対応いたしておりますので、ポスティングをご検討の際にはぜひ一度お気軽にご相談ください。
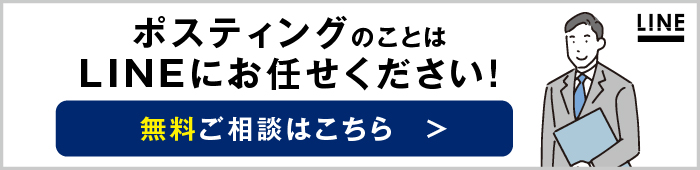
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 25年09月29日
25年09月29日