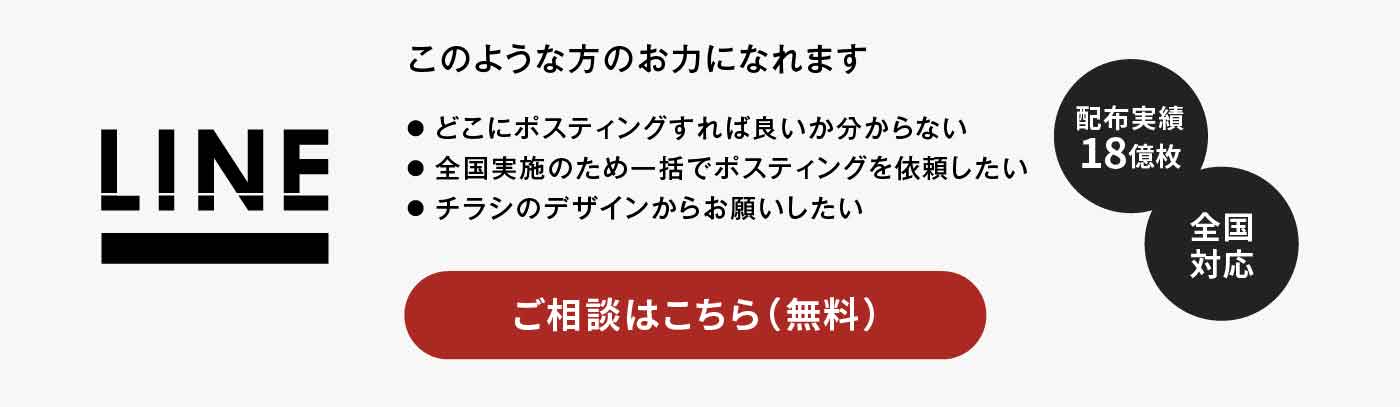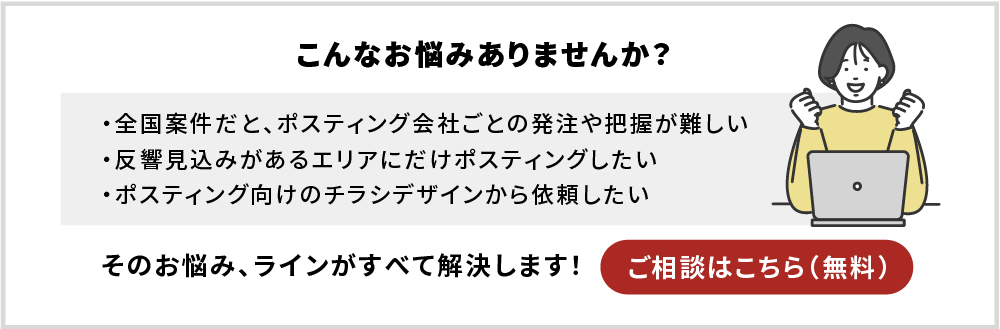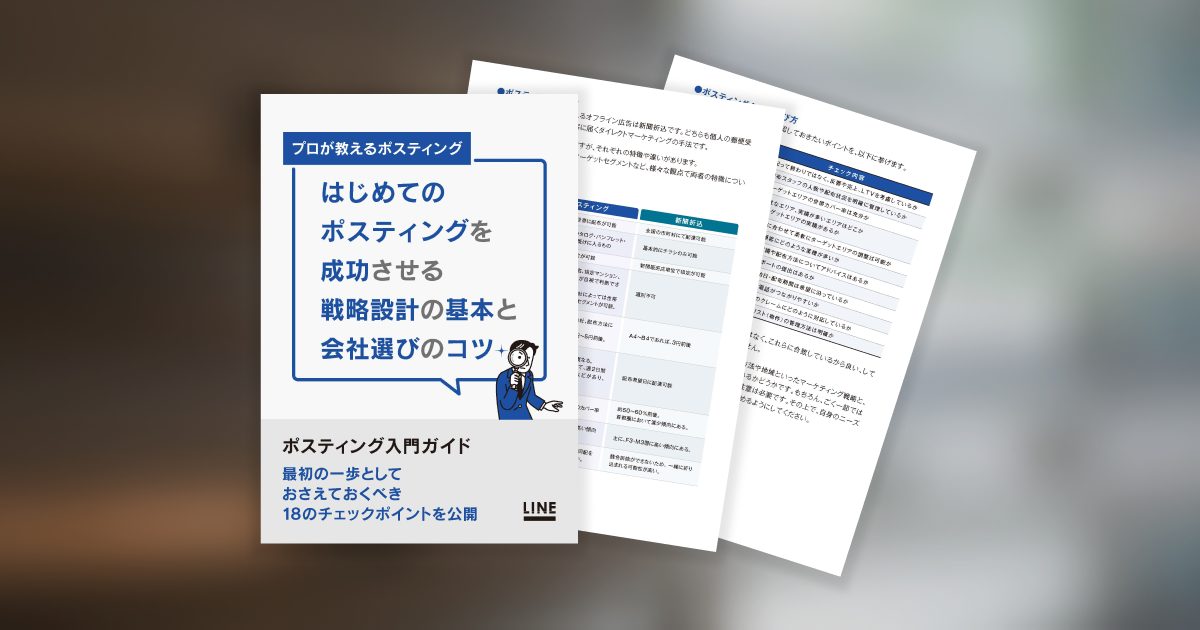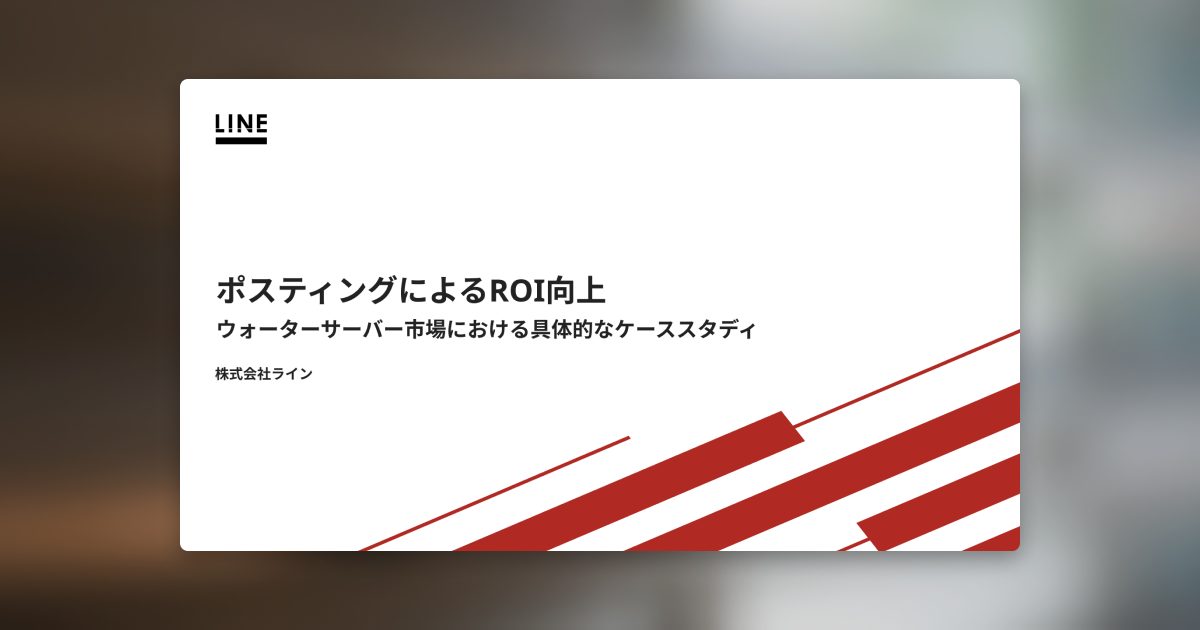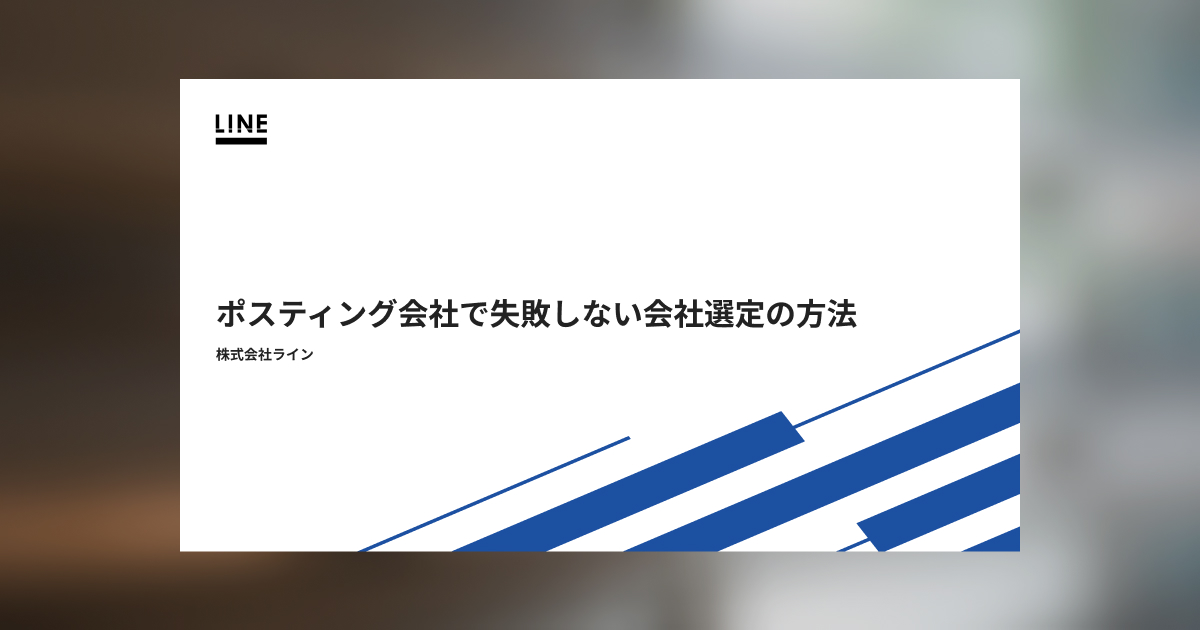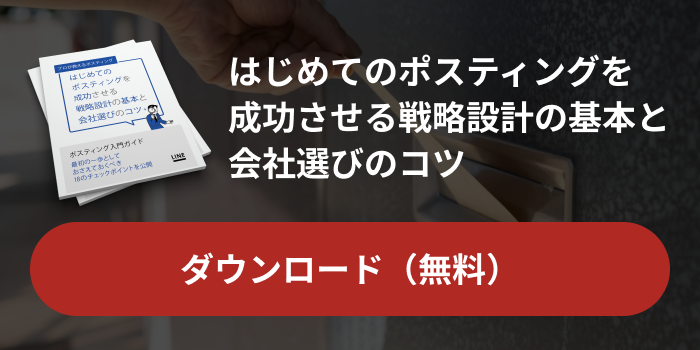ポスティングでクレームが入った!トラブルの種類や回避のための対策方法を解説


ポスティングは、地域密着型の販促手段として高い効果を期待できますが、間違った方法でポスティングを行うとクレームにつながる可能性があります。クレームにつながる原因や対処方法を理解していなければ、大きなトラブルに発展してしまう恐れもあるため注意が必要です。
本記事では、実際に起こり得るポスティングのクレームやトラブルの種類を紹介しながら、それらを未然に防ぐための具体的な対策方法を解説します。この記事を参考にすることで、ポスティングで発生するクレームを防ぎながら効果的な宣伝が可能になります。
目次
ポスティング人気エリア
\ポスティングを実施したいと思ったら /
「ポスティングをしたいけど、何から始めれば良いか分からない」という方は、ぜひ株式会社ラインにご相談ください。
エリアのご提案から配布のご手配はもちろん、過去の実績を生かしたチラシの制作や印刷、配布後のレポート管理や結果分析まで、すべての業務をお任せいただけます。
ポスティングで起きやすいクレームの種類と対策方法

ポスティングで実際に起こり得るクレームの種類は、主に以下の8つが挙げられます。
- 投函禁止物件なのにチラシが入っていた
- 共有部にチラシが散乱していた
- チラシがまとめて放置されている
- 過去にクレームを入れたのにまたチラシが入った
- 同じチラシを複数枚入っている
- チラシが濡れて入っていた
- 早朝・深夜にチラシが投函された
- 配布員の行動が不審に感じられる
対応次第では企業や店舗のイメージダウンにつながる恐れがあります。トラブルを未然に防ぐためにも、想定されるクレームの種類をあらかじめ把握し、それぞれに適した対策を講じることが大切です。ここでは、それぞれのクレームについての詳細と対策方法について詳しく解説していきます。
投函禁止物件なのにチラシが入っていた
ポストに「チラシお断り」「広告投函禁止」などの表示がある物件にチラシを投函してしまうと、高確率でクレームにつながる恐れがあります。居住者の意向を無視した配布は、「ルール違反」として強い不快感を与えることもあり、企業や店舗の印象を大きく損ねる原因になるため注意が必要です。
対策1:投函前に配布禁止の表示を確認する
現地でポスティングを行う前に、対象の物件に「広告投函禁止」などの表示がないかを必ず確認しましょう。特に、郵便受けや玄関周辺、インターホン付近などに掲示されていることが多いため、細かいチェックが必要です。
暗い時間帯に確認を行うと表示を見逃してしまう可能性があるため、できるだけ明るい時間に訪れることをおすすめします。
また、一度確認したからといって安心せず、配布前には毎回確認する習慣をつけましょう。物件のルールは変更されることもあるため、常に最新の状況を把握することが大切です。
対策2:配布禁止リストを作成して社内で共有する
過去にクレームがあった物件は、今後チラシを投函しないよう社内で「配布禁止リスト」として記録し、全スタッフで情報を共有することが大切です。
また、GPS付きの配布管理システムを活用すると、配布したエリアをリアルタイムで確認でき、禁止エリアに誤って配布していないかをチェックしやすくなります。
情報共有とシステム管理を併用することで、人的ミスを防ぎ、より確実なトラブル回避につながります。
共有部にチラシが散乱していた
マンションやアパートの共有スペースにチラシが散乱していると、住民から「見苦しい」「管理が行き届いていない」といった苦情が寄せられることがあります。
放置されたチラシは清掃の手間を増やすだけでなく、マンションの管理会社や住民との信頼関係を損なう要因にもなりかねません。こうしたトラブルを防ぐには、丁寧な配布とアフターケアが重要です。
対策1:適切な配布方法を徹底する
チラシがポストから抜け落ちないよう、以下の適切な配布方法を徹底することが基本です。
- ポストの奥までしっかり入れる
- 複数枚をまとめて投函しない
- 複数枚を投稿数必要がある場合はゴムバンドで束ねる
対策2:配布後の現場確認を実施する
配布が終わったら、その場で簡単な巡回を行い、チラシが散らばっていないかを確認することも重要です。もしチラシが落ちていたり、複数枚がポストから出ている状態を見つけた場合は、速やかに回収・投函を正しましょう。
特にクレームが発生しやすいエリアでは、配布スタッフだけでなく会社側でも定期的に現場確認を行うと、問題を早期に発見・対処しやすくなります。
チラシがまとめて放置されている
チラシが散乱しているわけではなく、何枚も束になった状態で放置されているケースもクレームにつながる原因の一つです。
集合住宅のポスト付近でよく見られる場合は、住民が不要なチラシをまとめて捨てている可能性がありますが、ポスト以外の場所や戸建て住宅周辺で発見された場合は、配布員による置き忘れや不適切な配布が疑われます。いずれの場合も、周囲に不快感を与え、企業のイメージを損ねる恐れがあるため注意が必要です。
対策1:ポスティング専用の回収ボックスを設置する
集合住宅の場合、不要になったチラシの放置を防ぐ手段として、「ポスティング専用の回収ボックス」の設置が効果的です。住民が不要なチラシを簡単に処分できるため、ポスト周辺にまとめて放置されるリスクを軽減できます。
ただし、開口部が広い一般的なゴミ箱を設置すると、チラシ以外のゴミも投棄される可能性があるため、チラシ専用である旨を明記したボックスがおすすめです。設置の際は、必ず物件の管理者に確認し、正式な許可を得る必要があります。
対策2:配布員への周知と現場確認の徹底を促す
ポスト以外の場所にチラシが束になって放置されていた場合は、配布員による置き忘れの可能性が高いため、関係者への周知を徹底しましょう。実際にクレームがあったことや、再発防止の重要性を伝えることで、配布への意識を高めることができます。
また、配布終了後には現場の確認を行い、手元に残っているチラシの枚数と配布記録を照合する習慣をつけることも効果的です。こうした基本の徹底が、クレームを防ぐ大きなポイントとなります。
過去にクレームを入れたのにまたチラシが入った
一度クレームを受けたにもかかわらず、同じ住所に再びチラシを投函してしまうと、非常に深刻なトラブルに発展する可能性があります。よくあるケースとして、投函禁止の張り紙はないが、投函しないでほしいという連絡が以前にあった場合が挙げられます。住民からすれば「無視された」「対応がなされていない」と受け取られ、企業や店舗に対する不信感が大きくなる可能性があります。
対策1:クレームがあった住所をリスト化する
まず大切なのは、一度でもクレームが発生した住所は即時にリスト化し、今後の配布から確実に除外する体制を整えることです。
Excelなどで管理する方法もありますが、ミスを防ぐためにはポスティング管理システムの導入がおすすめです。GPS機能付きのシステムであれば、禁止エリアへの配布をリアルタイムで確認・制限することができ、ヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減できます。
対策2:配布員への周知と再発防止の研修を行う
クレームの再発を防ぐには、配布員一人ひとりの意識改革も不可欠です。配布前に、クレーム履歴のある住所や注意が必要なエリアについてしっかりと周知し、「一度クレームが入った物件への再投函は厳禁」というルールを明確に伝えましょう。
また、配布スタッフを対象に、クレーム発生時の対応や再配布のリスクについて研修を行うことで、現場の意識を高め、トラブルの未然防止につながります。
同様のチラシが複数枚入っている
ポストを開けたときに、まったく同じチラシが2枚以上入っていると、クレームの原因になることがあります。特に、定期的にポスティングを行っている場合や複数人で手分けして作業している場合などにポスティング先が重複してしまうケースがあります。
対策1:GPS管理で配布ミスを防ぐ
複数のスタッフで同じエリアを担当する場合、配布エリアの重複を避けるために、GPSを活用した管理が有効です。あらかじめ地図アプリなどで配布エリアを細かく区切り、担当範囲を明確にしておくことで、スタッフ同士の配布重複を防ぐことができます。
また、エリアの境界線をスタート地点に設定すると、作業開始時点で重複リスクを減らすことが可能です。リアルタイムで配布状況が確認できるシステムを使えば、さらに精度の高い管理が実現できます。
対策2:指サックなどを使い投函ミスを防ぐ
同じスタッフが複数枚のチラシを誤って1つのポストに入れてしまう可能性もあります。これは用紙が薄かったり、乾燥する季節に指が滑りにくくなったりすることで起こりやすくなります。
こうした場合には、指サックの使用が効果的です。1枚ずつしっかりと掴めるため、無意識のうちに複数枚を投函するミスを防止できます。クレーム予防はもちろん、配布作業そのものの効率化にもつながるため、積極的に導入することをおすすめします。
チラシが濡れて入っていた
ポストを開けたときに、チラシが濡れていたり、文字や写真がにじんでいたりすると、受け取る側は不快に感じるだけでなく、せっかくの広告内容が読みづらくなり、反響率にも悪影響を与える可能性があります。さらに、他の郵便物まで濡れてしまった場合には、住民からの強いクレームにつながることもあります。
対策1:悪天候時の配布は控える
雨や雪、強風、台風といった悪天候時には、可能な限りポスティングを避けるのが原則です。どうしても配布が必要な場合には、チラシをビニール袋などで包み、移動中に濡れないようしっかりカバーする工夫が必要です。
ただし、チラシをビニールに包んだまま投函するのは避けましょう。ポスト内でビニールに残った水分が他の郵便物を濡らしてしまうリスクがあるため、大きなクレームに発展する恐れがあります。
対策2:チラシをポストの奥まで入れる
チラシがポストの投函口から少しでも外に出ていると、雨水や雪に直接触れて濡れてしまう可能性が高くなります。そのため、チラシは必ずポストの奥までしっかり差し込むことが重要です。
また、風で飛ばされたり抜け落ちたりするリスクも減るため、丁寧な投函がクレームの防止にもつながります。
早朝・深夜にチラシが投函された
ポスティングは基本的に静かな作業ですが、早朝(~6時)や深夜(20時~)といった時間帯では、わずかな物音でも響きやすく、住民の生活に不快感を与える恐れがあります。
また、不審な時間帯に人が敷地内にいると、「空き巣の下見かもしれない」「不審者ではないか」と不安に感じられ、警察への通報につながるケースもあります。トラブルを防ぐためにも、作業時間帯への配慮が不可欠です。
対策1:一般的な活動時間にポスティングする
ポスティングは、一般的な生活リズムに合わせた時間帯、午前9時~午後7時頃までの間に行うのが理想です。この時間帯であれば騒音トラブルや不審者扱いのリスクを最小限に抑えることが期待できます。
また、自治体やマンション管理会社がポスティングの時間帯を定めている場合もあるため、事前に確認し、ルールを遵守することを心がけましょう。
対策2:時間内に配り切れる量だけを用意する
配布スタッフに過度なノルマを課すと、「今日中に全部配り切らなければ」と焦ってしまい、時間外の配布を行ってしまう可能性があります。こうした状況を避けるためには、スタッフごとの実績や体力を考慮し、無理のない配布枚数を設定することが大切です。予定より余ったチラシは、次回に回す・回収するなどして、時間外配布を未然に防ぎましょう。
配布員の行動が不審に感じられる
マンションや住宅街でのポスティングで、配布員の行動が「不審者ではないか」と住民に疑われるケースがあります。例えば、敷地内で長時間滞在したり、同じ建物を何度も出入りしていると、「何をしているのか分からない」と不安に感じる人も少なくありません。状況によっては管理人に報告されたり、警察に通報されるトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
対策1:敷地内に入る前に投函の準備を整えておく
不審に思われないためには、敷地内に入ってからの滞在時間をできるだけ短くすることが重要です。そのためにも、投函する前にあらかじめチラシを整理し、スムーズに配れる状態にしておきましょう。
カバンの中からチラシを探したり仕分けをしていると、作業に時間がかかり、誤解を生む原因になります。また、事前にエントランスの場所やポストの配置を把握しておくと、より迅速に対応できます。
対策2:名刺を用意しておく
住民から声をかけられたときの備えとして、会社名や連絡先を記載した名刺を持ち歩いておくと信頼感が高まり、トラブルを回避しやすくなります。
また、マンションやオフィスビルの場合は配布前に管理人へ一声かけておくのも有効です。事前に挨拶をしておけば、配布中の行動に対する誤解が生じにくく、安心して作業できる環境を整えることができます。
ポスティングでクレームが起きたときの対応方法

ポスティングでクレームが起きたときの主な対応方法は、以下の4つです。
- 早急に対応する
- どのような対策をしているのかを伝える
- 感情的な相手にも冷静に対応する
- クレーム後は絶対にポスティングをしない
ポスティングでは、どれだけ注意をしていてもクレームにつながる可能性があります。相手にこれ以上不快な思いをさせないためにも、正しいポスティングクレームの対応方法を理解しておきましょう。
早急に対応する
ポスティングによってクレームが発生した場合には、早急に対応することが大切です。すぐに謝罪を行うことで、相手にも誠意が伝わりやすくなります。対応が遅くなればなるほど、クレームを入れた側も「真面目に対応してくれない」と感じてしまい、さらに大きなクレームに発展する可能性があります。
また、ポスティング会社に配布を依頼している場合でも、チラシに記載されている自社の連絡先に連絡が入ることがあります。その場合は、速やかにポスティング会社にクレームがあった旨を伝え、適切に対応してもらいましょう。
どのような対策をしているのかを伝える
ポスティングによってクレームが発生した場合には、どのような対策をしているのかを伝えることも大切です。ただ謝罪するだけでは、相手に信用してもらえない可能性があります。どのような対策をし、今後は同じようなクレームにつながらないように精進することを伝えましょう。
また、対応時の言葉遣いにも注意が必要です。例えば「クレーム」と伝えるのではなく「貴重なご意見」といったように言い換えて伝えましょう。言葉遣い1つで、不快感を与えてしまう恐れもあるため、慎重に対応することが大切です。
感情的な相手にも冷静に対応する
ポスティングによるクレームが発生する際、多くの場合は相手に強い怒りや不満があり、感情的になっているケースが少なくありません。突然の投函に驚いたり、何度も同じようなトラブルを経験していたりすると、冷静な話し合いが難しい場合もあります。
そのようなときは、落ち着いた態度で対応することが大切です。まずは相手の話を最後まで聞き、誠実に受け止める姿勢を見せましょう。こちらが感情的に反応してしまうと、事態がさらに悪化してしまう恐れがあります。
冷静で丁寧な対応を心がけることで、相手の怒りも和らぎ、早期の解決につながります。また、誠意ある対応は会社の信頼にも直結します。
クレーム後は絶対にポスティングをしない
クレームがあった住宅には、今後ポスティングを絶対にしないことも重要です。いくら注意していても、再度クレームにつながるようなことがあれば、会社のイメージダウンにつながる可能性が高いです。
ポスティング会社に配布を依頼している場合は、ポスティング会社にも今後は投函しないように必ず共有しましょう。
– 関連記事 –
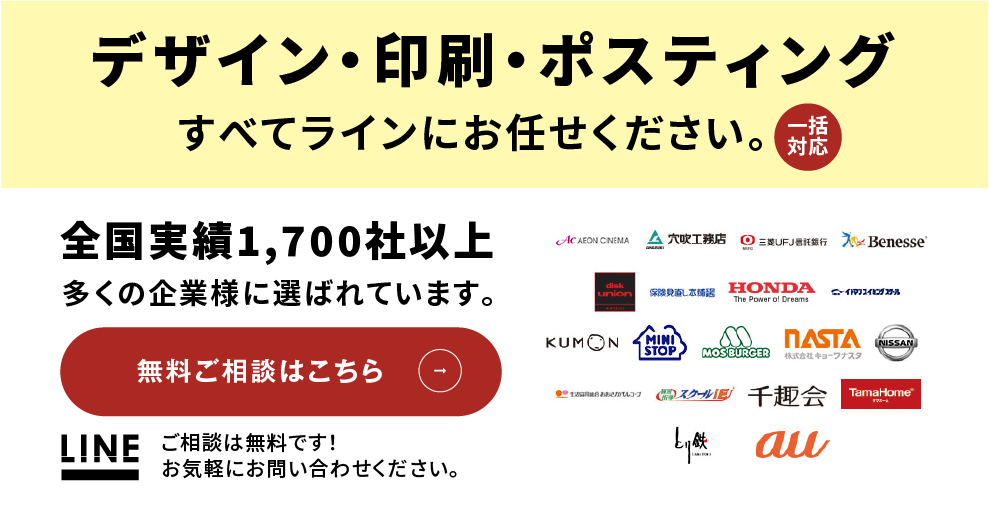
ポスティングをして違法になるケース

ポスティングを行って違法になるケースとしては、以下の3つが挙げられます。
- 住居に不法侵入した
- 公序良俗に違反する内容のチラシを投函した
- 他のチラシを取り出した
ポスティングを行うこと自体には違法性はありませんが、ポスティングのやり方や内容によっては、違法と判断されて通報される可能性があります。未然にクレームを防ぐためにも、違法になるケースを理解しておきましょう。
住居に不法侵入した
ポスティングのためだからといって、不法に住居に侵入した場合には、違法になる可能性があります。ポスティングを行うためには、建物の中に入らなければいけませんが、建物によっては投函禁止の張り紙があり、無視して侵入すると、住居侵入罪に問われる可能性があります。
また、管理人や受付の方などに注意をされたにも関わらず、無視して侵入した場合にも、通報される恐れがあるため注意しましょう。
公序良俗に違反する内容のチラシを投函した
公序良俗に反する内容のチラシをポスティングした場合にも、違法になります。基本的に、公序良俗に違反した内容のチラシは、ポスティングをしないことが望ましいです。ポスティングをしてしまうと、風俗営業法違反や迷惑防止条例違反になります。
ポスティングを行う前にチラシの内容を確認し、法律に違反していないかどうかを必ず確認しましょう。
他のチラシを取り出した
ポスティングを行う際に、他のチラシを取り出してしまうと違法になる可能性があります。ポストが投函物でいっぱいになっている場合や他のチラシに埋もれないようにしたいと考えた場合に、他のチラシを取り出してしまうケースがあります。
他のチラシの取り出しは、軽犯罪法に該当します。さらに、ポストを壊してしまった場合には、器物破損として通報される恐れもあるため注意が必要です。
ポスティングでクレームを起こさないための予防法

主なポスティングのクレーム予防方法は、以下の3つです。
- 管理人に許可を取ってからポスティングを行う
- クレームが多いエリアの情報をまとめておく
- 事前に配布計画を立てる
クレームなくポスティングをスムーズに行うためには、予防法を理解しておくことが大切です。
管理人に許可を取ってからポスティングを行う
ポスティングによるクレームを未然に防ぐためには、管理人に許可を取ることが大切です。管理人にポスティングの許可を取っておけば、クレームは予防できます。特に、管理人が在住するマンションでポスティングを行う場合には確認を行いましょう。
マンションによっては、セキュリティ面から、ポスティング自体を禁止としている場合もあります。トラブルを予防するためにも、許可を取ってからポスティングを行うことをおすすめします。
– 関連記事 –
クレームが多いエリアの情報をまとめておく
ポスティングによるクレームを未然に防ぐには、過去にトラブルが多かった地域や物件の情報をしっかりと記録し、社内で共有しておくことが効果的です。どのエリアでどのようなクレームが発生したのかを把握することで、同じトラブルを防ぐことができます。
特に、管理会社や住人がポスティングに対して厳しい姿勢を取っている地域では、細心の注意が必要です。場合によっては、そうした物件やエリアを配布リストから外すことも検討しましょう。
事前に配布計画を立てる
ポスティングは、無計画に実施すると深夜の投函や禁止エリアへの誤配など、思わぬクレームにつながる恐れがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、事前に配布計画を立てておくことが重要です。
具体的には、配布エリア・配布時間・配布人数をもとに、配布枚数やスケジュールを細かく管理しましょう。時間帯に配慮すれば騒音によるクレームを避けられ、エリアや人数の調整によって重複配布や投函忘れのリスクも抑えられます。
また、雨天時や悪天候時の対応方針もあらかじめ決めておくことで、濡れたチラシによるクレームも予防できます。しっかりとした計画を立てておくことで、効率的かつトラブルの少ないポスティングが実現できます。
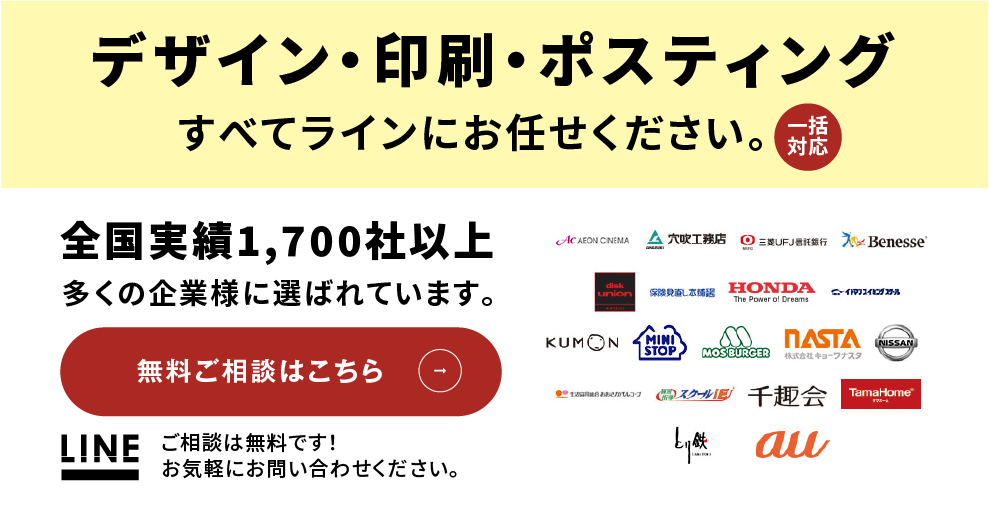
クレームに対応したポスティングなら株式会社ラインへ

クレームが発生した場合、どのような対策をするかによって、会社のイメージにも大きく影響することを理解しておきましょう。また、可能な限りクレームを発生させないよう、今回の記事を参考にしてポスティングを実施することをおすすめします。
また、クレームを予防しながらより効果的なポスティングを行いたいと考えている場合は、株式会社ラインにご相談ください。株式会社ラインでは、独自のクレーム対応マニュアルを共有しているほか、全国7,000件以上の投函禁止リストを保有しており、過去にクレームが発生した物件へのポスティングは行わないように徹底しています。万が一クレームが発生した場合も、謝罪、引取り等迅速に対応しております。
ポスティングを行う上でご不安がある場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
– 関連記事 –
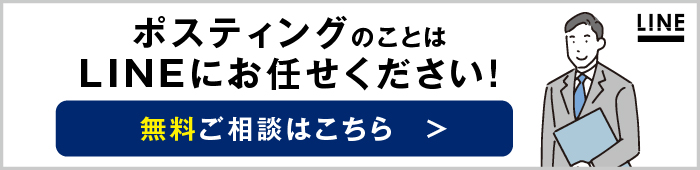
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 25年10月02日
25年10月02日