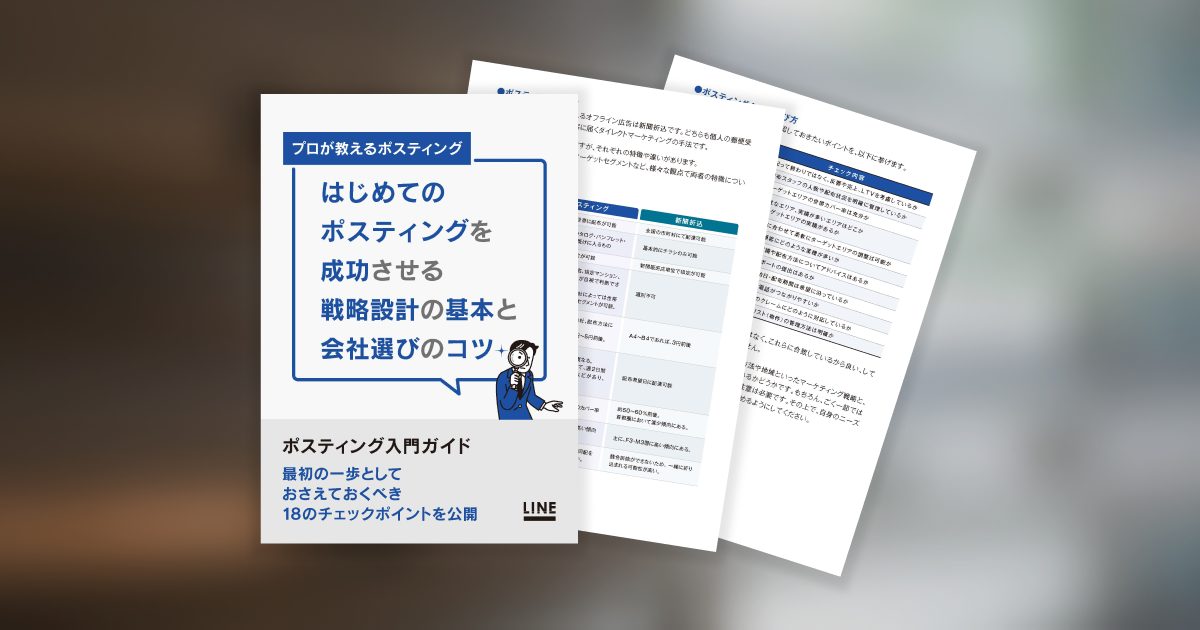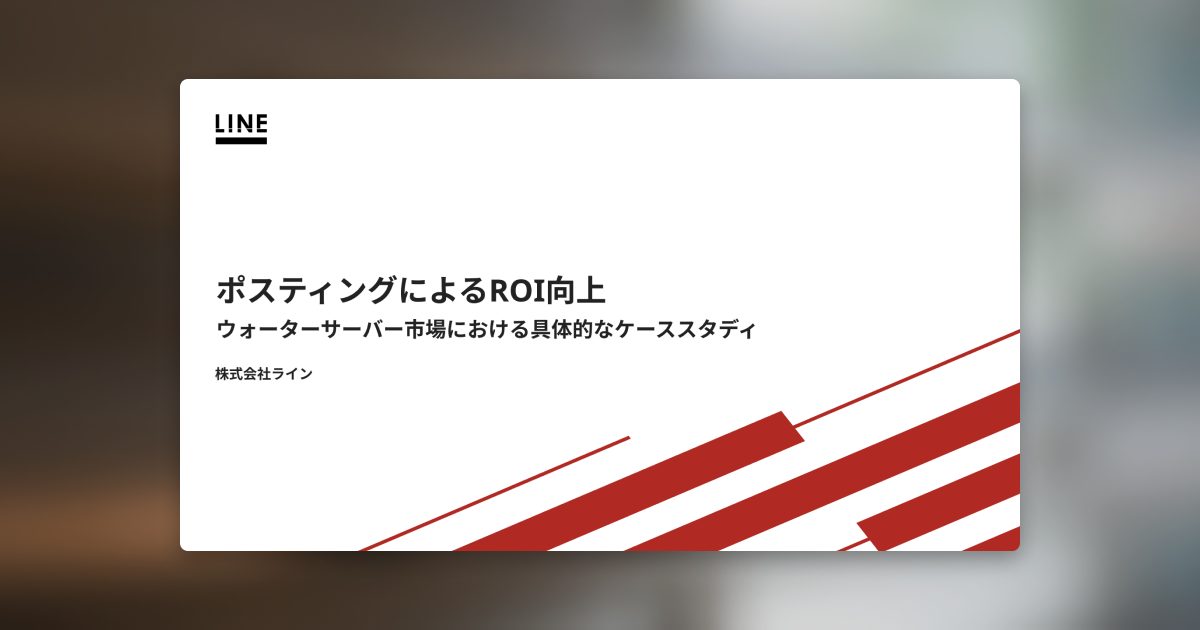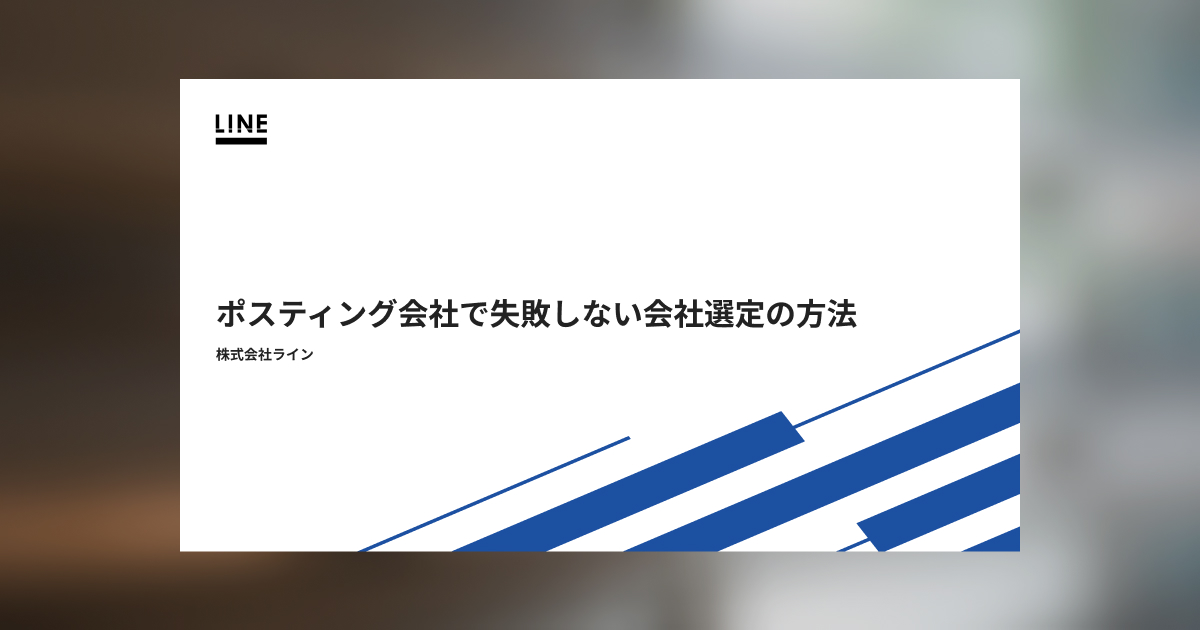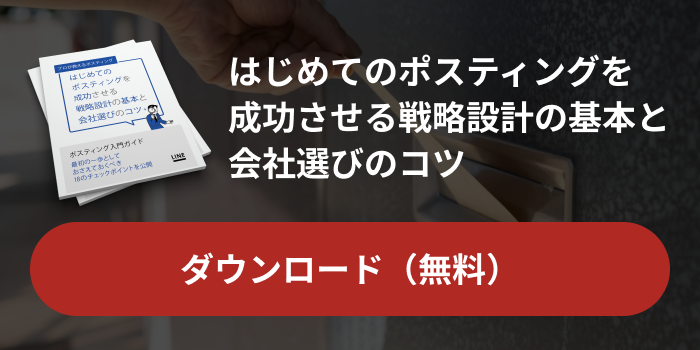反響が変わるチラシの配色術!色の基本とコツを紹介

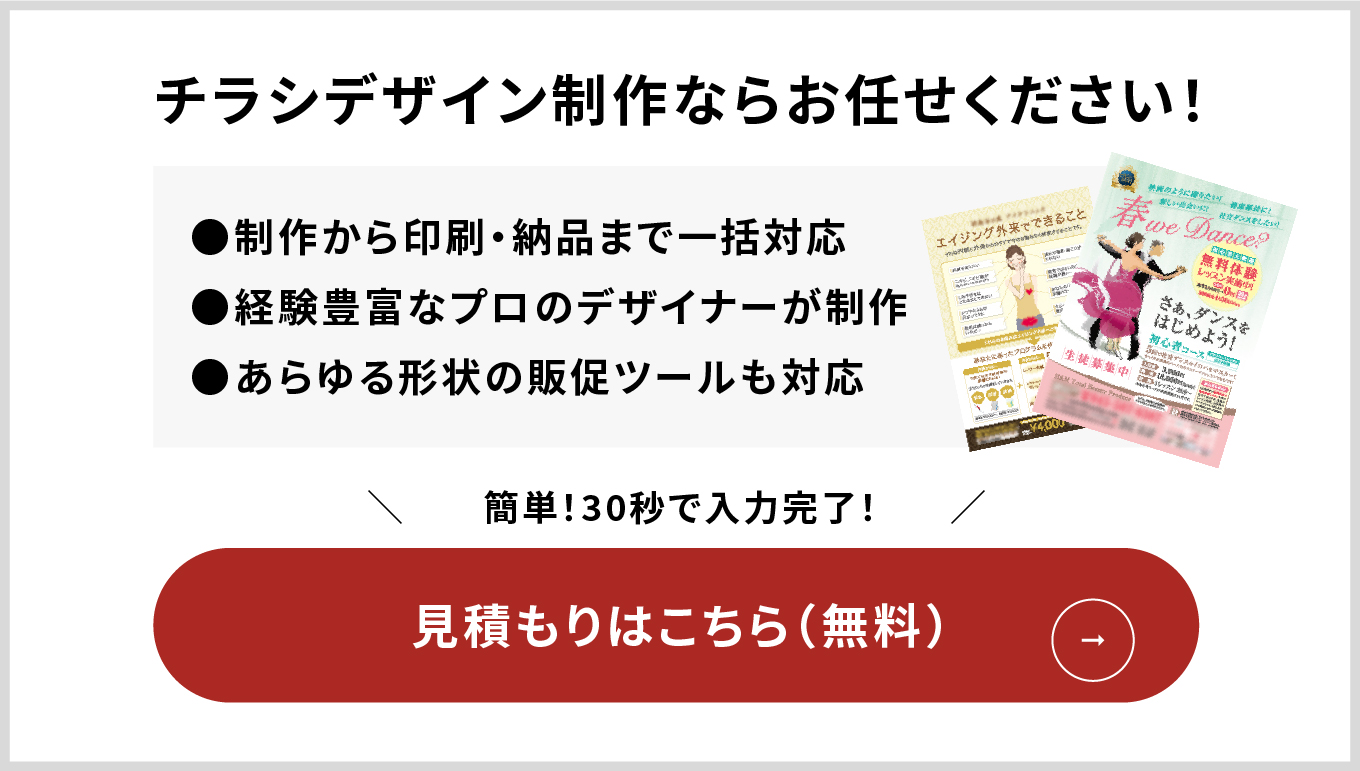
チラシを作って配布してみたものの、期待する反応が得られなかったり、伝えたいことがうまく伝わっていないと感じた経験はありませんか?
その原因のひとつとして、意外と見落とされる「配色」が関係しているかもしれません。
色は、見る人の心理に無意識のうちに影響を与える重要な要素です。どんなに内容が優れていても、配色によっては魅力が半減してしまったり、逆に強く印象づけられることもあります。チラシの印象や情報の伝わりやすさを左右する色の力を、正しく理解することが、より反響を高めるために重要になります。
この記事では、チラシ作成における配色の基本的な考え方をはじめ、目的やターゲットに応じた色の選び方、プロが実践している配色テクニック、さらには避けるべきNG配色の例まで、具体的に分かりやすく解説していきます。
目次
配色の基本ルール・考え方

チラシにおける「配色」とは、2色以上の色をバランスよく組み合わせ、情報を効果的に伝えるためのテクニックです。色には心理的な影響力や視認性があるため、単に好みの色を並べるのではなく、ルールや基本的な考え方を押さえて使うことが大切です。
ここでは、配色の基本となる「色の三属性」と「配色比率の法則」について詳しく解説します。
色の三属性
色には「色相・彩度・明度」という3つの属性があります。これらのバランスを理解することで、印象的で見やすいチラシ作成が可能になります。
| 色相 (しきそう) | 赤・青・緑など、色味そのものを指す。暖色系(赤・オレンジなど)は温かみや 活発な印象を、寒色系(青・緑など)は落ち着きや信頼感を与える傾向がある。 |
|---|---|
| 彩度 (さいど) | 色の鮮やかさを表す指標で、彩度が高いほどビビッドで目を引く色に、彩度が 低いほど落ち着いたくすんだ色になる。 |
| 明度 (めいど) | 色の明るさの度合いを示す。明度が高いと白に近くなり、明るくやさしい印象に なる。反対に明度が低くなると黒に近づき、重厚で引き締まった印象になる。 |
三属性をうまく使い分けることで、ターゲットや目的に合ったトーンを作り出すことができます。
配色比率「70:25:5」の法則
配色では、色の組み合わせだけでなく、「使う比率」も重要なポイントになります。よりバランスの取れた色使いを実現するために、多くの場面で活用されているのが「70:25:5の法則」です。
| ベースカラー(70%) | チラシ全体の背景や基調として使う色。視覚的な安定感を与えるため、落ち着いた色調を選ぶのが一般的。 |
|---|---|
| メインカラー(25%) | タイトルや見出しなど、伝えたい内容を際立たせるための主役の色。チラシの印象を決定づける重要な役割を持つ。 |
| アクセントカラー(5%) | ボタンや価格表示など、特に目を引かせたい部分に使う差し色。少量でも強い印象を与えるため、彩度や明度の高い色を選ぶと効果的。 |
これらの比率を意識することで、色数が多くても統一感のあるチラシを作成でき、情報の優先順位も明確になります。
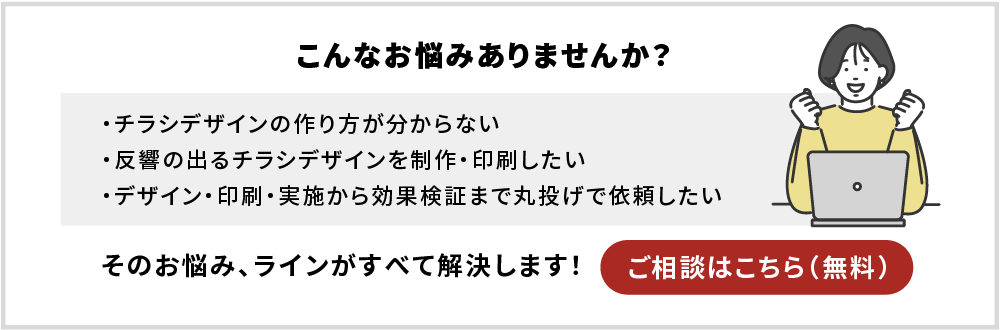
チラシを上手に配色するコツ

色使いは、チラシの印象や集客効果も左右する可能性があります。ここでは、チラシを上手に配色するためのポイントを3つご紹介します。
- 色数を絞る
- コントラストを意識する
- ターゲットに合わせた色選びをする
基本のルールを押さえたうえで、さらに効果的な仕上がりにするためには、上記ポイントを意識してみましょう。
色数を絞る
配色で迷ったときは、「色数を絞る」ことを意識しましょう。基本的には、3色程度に抑えるのが理想的です。色を使いすぎるとチラシ全体が散漫な印象になり、情報が伝わりにくくなる恐れがあります。
同系色や類似色を組み合わせることで、自然なまとまりが生まれ、統一感のあるデザインになります。
コントラストを意識する
コントラスト(対比)も重要なポイントのひとつです。特に背景と文字の明度差は大きくとるように意識しましょう。これにより、読みやすさが高まり、伝えたい情報がスムーズに目に入ります。
また、キャンペーン価格やキャッチコピーなど重要な部分は、配色でしっかりと目立たせることが大切です。ただし、目立たせすぎて全体のバランスが崩れないように注意しましょう。
ターゲットに合わせた色選びをする
ターゲットに合わせた色選びも、チラシ配色の重要なポイントです。
たとえば、若年層向けであればポップなビビッドカラー、中高年層向けであれば落ち着いたトーンが好まれる傾向があります。また、女性向けにはやさしいパステルカラー、男性向けにはシックな色合いが効果的な場合もあります。
さらに、チラシの内容や業種(例:美容、飲食、医療など)に合った配色や、季節・イベント(例:春は桜色、夏は爽やかなブルー系など)を取り入れることで、共感を得やすくなる可能性があります。
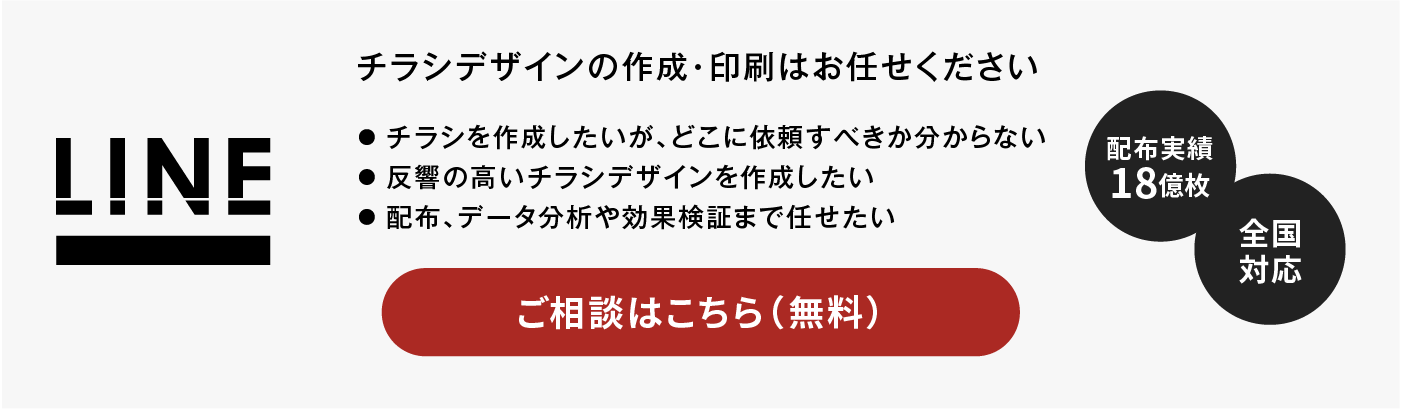
【パターン別】チラシ配色のイメージ

チラシの印象は、配色によって大きく左右されます。ここでは、目的やターゲットに応じた配色パターンを3つご紹介します。
- 明るく楽しい印象
- 高級感のある印象
- ナチュラルな印象
それぞれの配色が与える印象を理解し、適切に使い分けることで、チラシの魅力をさらに高めることが期待できます。
明るく楽しい印象
明るく親しみやすい雰囲気を演出したい場合は、明るいトーンや暖色系の色(赤・黄・オレンジなど)を中心に使いましょう。ポップで元気な印象になり、特に子ども向けのイベントやファミリー層をターゲットとしたチラシにおすすめです。
また、白やパステルカラーを背景や余白に使うことで、軽やかさと清潔感を加えられます。全体的に開放感のあるデザインに仕上がるため、楽しい気分を引き出したいシーンにおすすめです。
高級感のある印象
高級感や洗練されたイメージを演出したい場合は、黒・ゴールド・ネイビーといった深みのある色をメインに使うと効果的です。彩度を抑えた落ち着いたトーンにすることで、品のある印象に仕上がります。
さらに、アクセントとしてメタリックカラーや光沢感のある色を加えると、高級感が一層際立ちます。美容・宝飾・不動産など、信頼感や特別感を演出したい業種におすすめの配色です。
ナチュラルな印象
自然で安心感のあるチラシを作りたいときは、アースカラー(緑・茶・ベージュなど)を基調にした配色がおすすめです。柔らかいトーンを使うことで、温もりや落ち着いた雰囲気が伝わりやすくなります。
ナチュラル系の配色は、オーガニック製品やリラクゼーション、健康関連のチラシと相性がよく、木目や植物など自然素材のイメージと組み合わせると、さらに統一感のあるデザインに仕上がります。
チラシ配色のNG例

優れた内容のチラシであっても、配色を誤ってしまうと読み手の興味を引けない可能性があります。ここでは、チラシ作成においてよく見られる配色のNGパターンを3つご紹介します。
- 原色を多用する
- 色数が多すぎる
- ハレーションを起こしている
避けるべきポイントを把握し、読みやすく効果的なチラシ作りに役立てましょう。
原色を多用する
赤・青・黄といった原色を多く使いすぎると、色の刺激が強すぎて読み手に負担をかけてしまいます。視認性が高いというメリットもありますが、使い方を誤るとチラシ全体が落ち着きのないチグハグな印象になる恐れがあります。
また、配色のバランスが崩れることで、伝えたい情報が目立たず、埋もれてしまう可能性もあります。原色はアクセントとしてポイント的に使うのが効果的です。
色数が多すぎる
目立たせたいという思いから、多くの色を使ってしまうケースも注意が必要です。色数が多くなると情報が散乱し、読み手はどこを見ればよいのか分からなくなります。
結果として、チラシ全体が雑然とした印象になり、統一感も失われてしまいます。重要なポイントが埋もれてしまうリスクもあるため、使う色は基本3色程度に抑えることをおすすめします。
ハレーションを起こしている
ハレーションとは、色同士がぶつかり合い、目に強い刺激を与えてしまう状態です。とくに、赤×青や緑×紫などの補色同士、あるいは明度差が小さい色を組み合わせると、チラシが見づらくなってしまいます。
このような配色は、文字が読みにくくなったり、視認性が下がったりする原因となり、内容が十分に伝わらなくなる可能性があるため、視覚的に落ち着いた配色を心がけましょう。
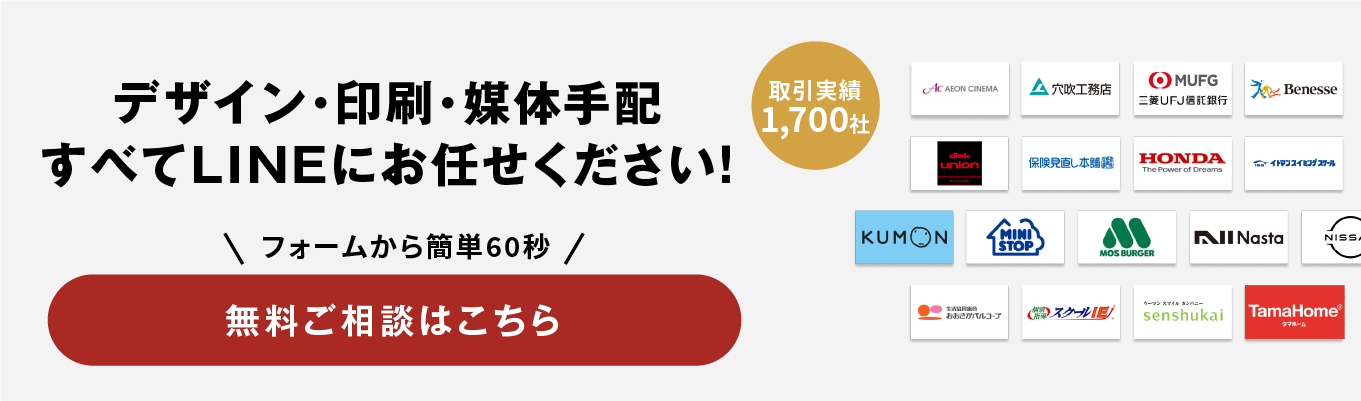
チラシの配色に役立つ資格「色彩検定・色彩コーディネータ」
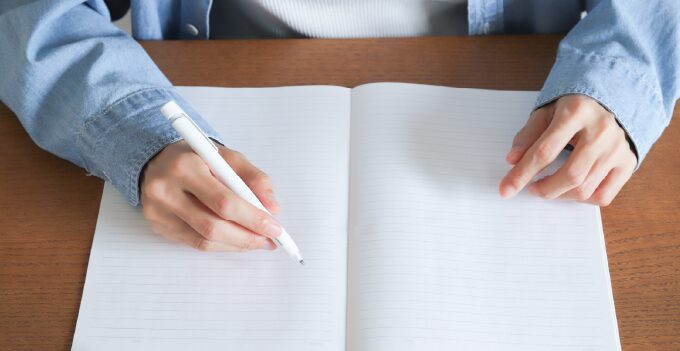
チラシの配色については、資格取得を通じてスキルを磨いてみるのも一つの方法です。特にこの分野において専門的な知識を身につけたいと考えている方には、「色彩検定」や「色彩コーディネーター」といった資格がおすすめです。これらの資格は、単なる色の知識だけでなく、配色の理論や実務に活かせるスキルを体系的に学べる点が大きな魅力です。
色彩検定は、文部科学省後援の公的資格であり、色の三属性や配色のバランス、心理的効果などを総合的に学ぶことができます。初級から上級まで段階的にレベルが設定されており、自分の目的に合わせて学習を進められます。
一方、色彩コーディネーターは、実際のデザインや商品企画、販促ツールの制作現場で即戦力となるような実践的な知識や技能を習得できる資格です。チラシのデザインだけでなく、ファッションやインテリア、商品パッケージなどにも応用できるため、幅広い分野で活用されています。
これらの資格を取得することで、配色に対する理解が深まり、専門性や信頼性が高まるため、クライアントからの評価にもつながりやすくなります。チラシの効果をより引き出したい場合やデザインスキルを高めたい場合に、ぜひ検討してみてください。
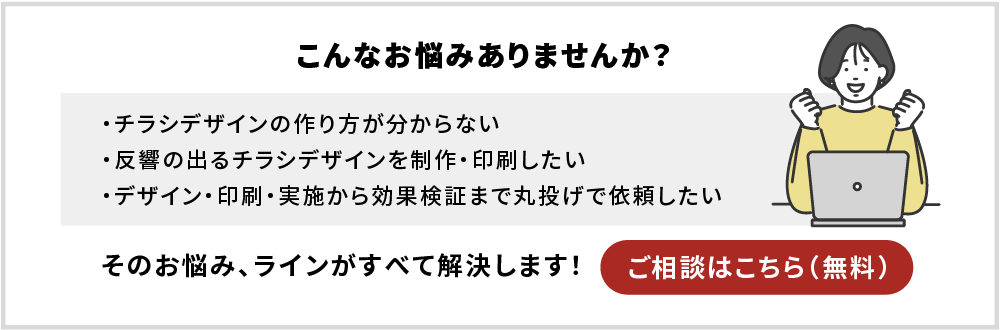
チラシの配色に役立つツール

配色に自信がない場合や、色の選び方に迷ったときは、配色支援ツールを活用するのがおすすめです。ここでは、チラシ作成に役立つ代表的なツールを3つご紹介します。
- Adobe Color CC
- Color Supply
- Color Hunt
これらのツールは、いずれも無料で利用でき、色の組み合わせを簡単に視覚化できるため、初心者からプロまで幅広く活用されています。
Adobe Color CC
Adobeが提供する「Adobe Color CC」は、カラーホイールを使って簡単に配色パターンを作成できるツールです。補色や類似色などのバランスを考慮した組み合わせを自動で提案してくれるため、デザイン初心者でも安心です。
さらに、世界中のデザイナーが作成した配色パレットを閲覧できるのも大きな魅力です。トレンドカラーを取り入れた配色や、業種別に参考になる例が豊富に揃っています。作成したパレットは保存・共有も可能で、チームでのチラシ作成にも便利です。
Color Supply
「Color Supply」は、色の組み合わせを視覚的に確認しながら配色パターンを選べるツールです。色を選ぶだけで、補色やトライアド(3色のバランス)など、さまざまな配色スタイルが自動で表示されます。
操作はシンプルで、直感的なUIが特徴です。文字色や背景色の組み合わせなど、チラシの見やすさに直結するポイントも視覚的に確認できます。
Color Hunt
「Color Hunt」は、世界中のユーザーが投稿した配色パレットを自由に閲覧・活用できるサイトです。プロが投稿した配色や、実際に使用されたトレンドカラーが多数掲載されており、見ているだけでもデザインのインスピレーションが湧きます。
気に入ったパレットはそのままコピーして利用可能で、トレンドや人気順での検索もできるため、最新のデザイン感覚を取り入れたいときに便利です。
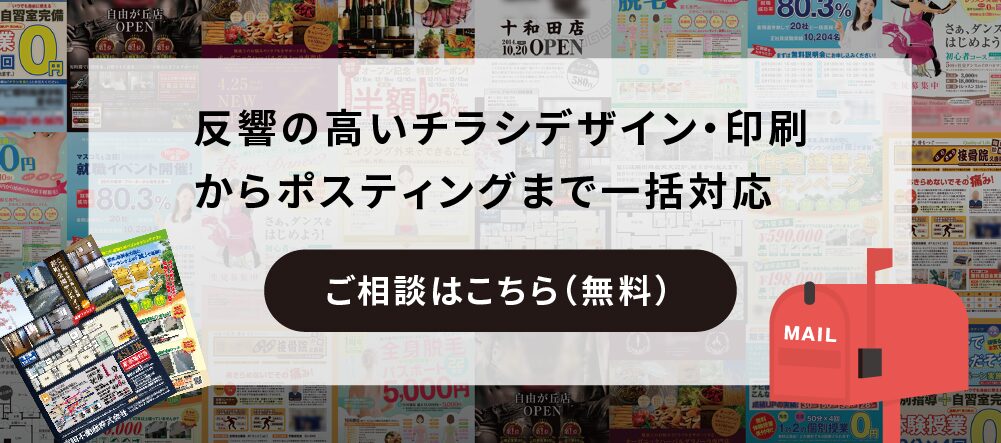
配色効果を活かしてターゲットの心に響くチラシを作ろう

チラシ作成において、「配色」は単なる見た目の問題ではなく、第一印象を左右し、情報の伝わりやすさや反響率に直結する重要な要素です。
配色の基本ルールをしっかりと理解し、意図を持って色を使い分けることができれば、より反響の高いチラシの作成が可能になります。
配色を工夫することで、チラシの印象は大きく変わり、ターゲットの心に自然と訴えかける力が生まれます。ぜひこの記事でご紹介した内容を参考に、より効果的な配色を意識してみてください。
チラシを初めて作成する場合や、思うような効果が得られないとお困りの場合は、株式会社ラインにぜひご相談ください。
チラシの配布実績18億枚以上の実績があるラインでは、プロのデザイナーが在中しており、豊富な実績を活かしたデザインのご提案をさせていただきます。配色について不安がある場合や、チラシ作成に工数が割けない場合など、ご相談だけでもお受けできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
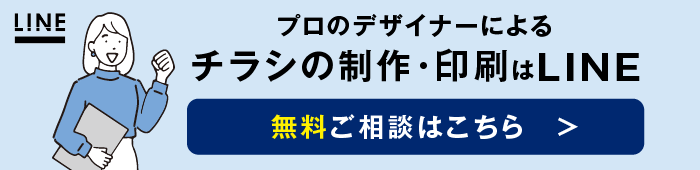
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 25年10月22日
25年10月22日