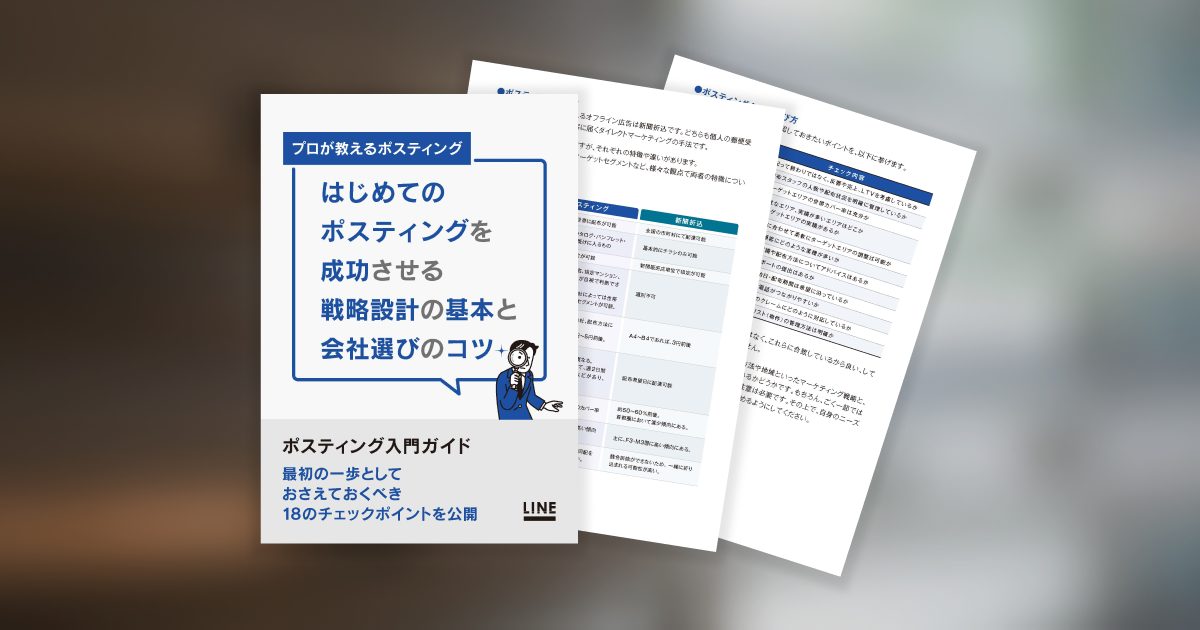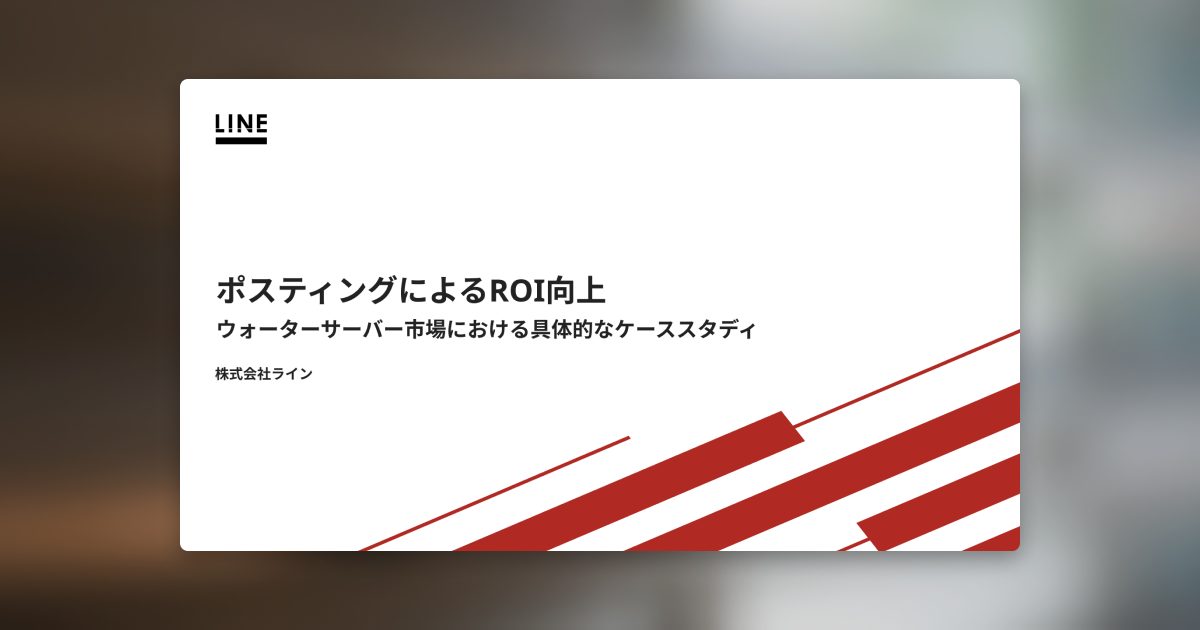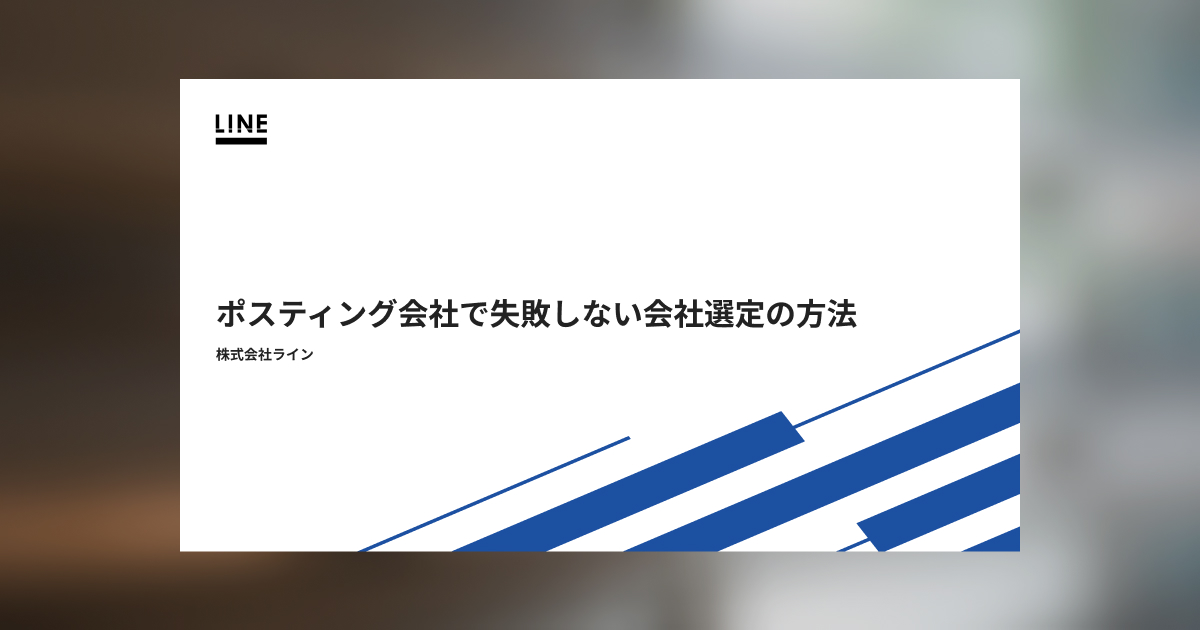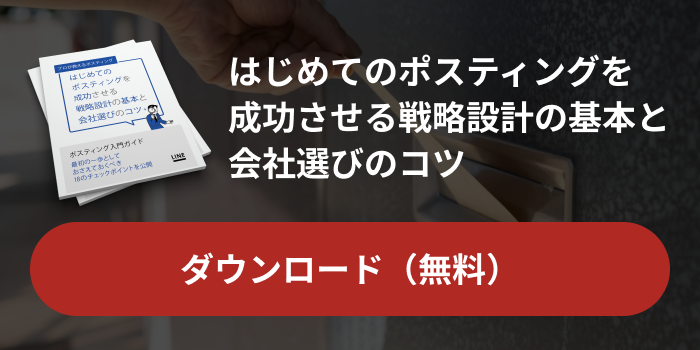助成金や補助金でチラシ広告を作成する方法|活用するメリットや注意点を分かりやすく解説

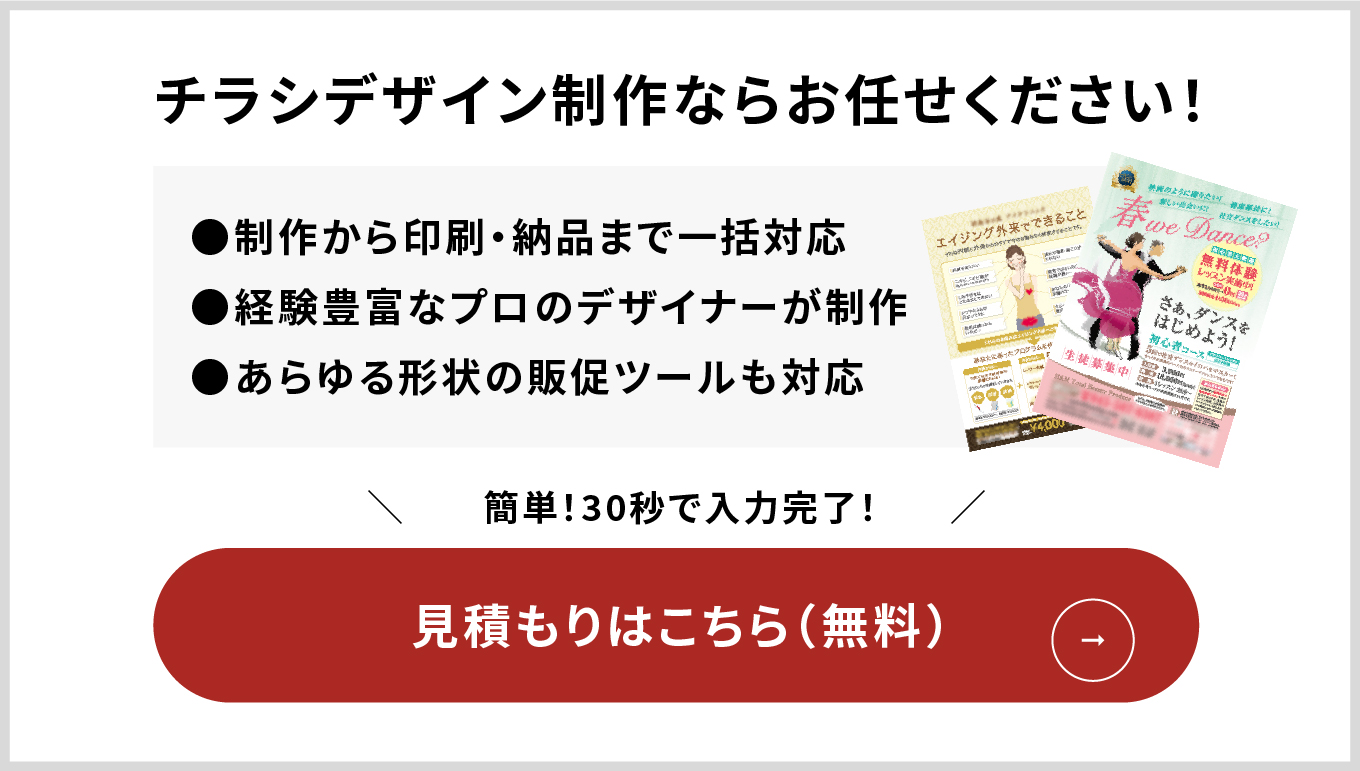
助成金や補助金を利用してチラシ広告を作成することができれば、多くのメリットを得られる可能性があります。資金面はもちろん、ビジネスチャンスをさらに拡大することにも繋がります。ただし、助成金や補助金を利用するためには、条件や対象となる範囲を理解する必要があります。
この記事では、チラシ広告に使える助成金や補助金の概要やメリット、使用する際の注意点を解説します。本記事を参考にすることで、助成金や補助金を有効活用してチラシ広告の作成が行なえる可能性があります。※
※2025年時点での情報になります。助成金や補助金は定期的に見直されているため、記載内容から変更されている場合があります。
目次
\助成金や補助金を活用してチラシを作成したいとお考えの方は/
「反響のあるチラシを作成したい」「チラシの作り方が分からない」という場合は、株式会社ラインにぜひご相談ください。
ラインでは、豊富な実績を活かして、より反響が得られるクリエイティブの作成、印刷までを一括でご依頼いただけます。
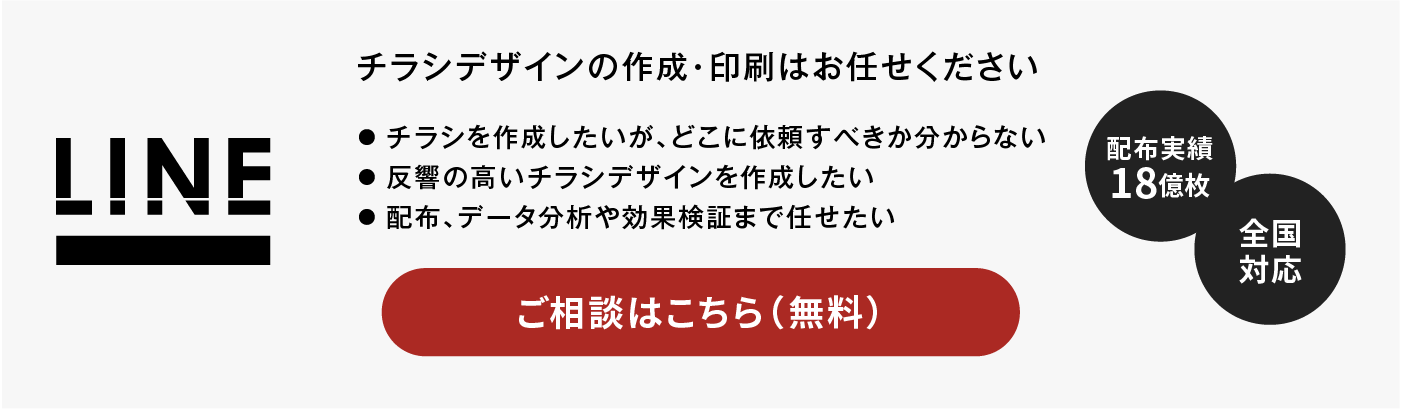
助成金や補助金でチラシ広告を制作する方法

チラシ広告の作成には一定のコストがかかりますが、助成金や補助金を活用すれば、費用負担を軽減しながら効果的な広告を実施できる可能性があります。
助成金・補助金を利用する際は、基本的に以下のステップで進めます。
- 申請可能な助成金や補助金を探す
- 大正の助成金事業に申請する
- 承認を受ける
- チラシを作成する
- 費用を請求する
申請内容が審査され、承認を受けることで初めて助成金・補助金を活用できるようになります。審査に通らないと支給されないため、チラシ作成の前に必ず申請を行いましょう。事前に対象となる制度を確認しておくことで、予算の計画も立てやすくなります。
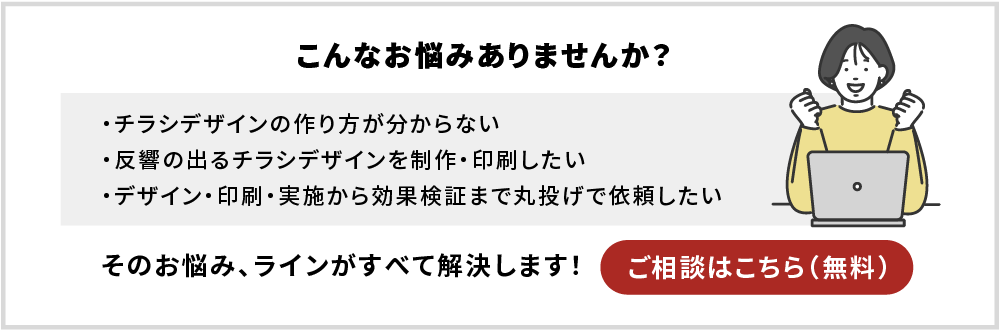
助成金と補助金の違い

助成金や補助金は、主に国や自治体が支給する資金支援制度のことです。助成金や補助金の利用を検討する場合は、それぞれの概要を理解しておく必要があります。
助成金と補助金とでは、以下のように支給する目的・条件・タイミングが異なります。
| 項目 | 助成金 | 補助金 |
|---|---|---|
| 目的 | 雇用促進・人材育成など社会政策に基づく支援 | 事業の成長や設備投資など具体的なプロジェクトを支援 |
| 支給条件 | 基準を満たせば原則受給可能(一部審査あり) | 競争型で審査あり、承認前に採択される |
| 支給タイミング | 事業実施後に申請、支給される | 事業完了後に実績報告を提出し、審査後に支給 |
どちらも事業活動を支援するための資金ですが、助成金と補助金は上記のようにに違いがあります。一般的に助成金は要件を満たせば受給しやすく、補助金は審査制で競争があるのが特徴です。
また、これらの資金は国や自治体だけでなく、一部の民間団体が支給している場合もあるため、実施主体を確認することが大切です。 支給条件も制度の種類や年度ごとに変わることがあるため、最新情報は公式サイトや商工会議所などでチェックしましょう。
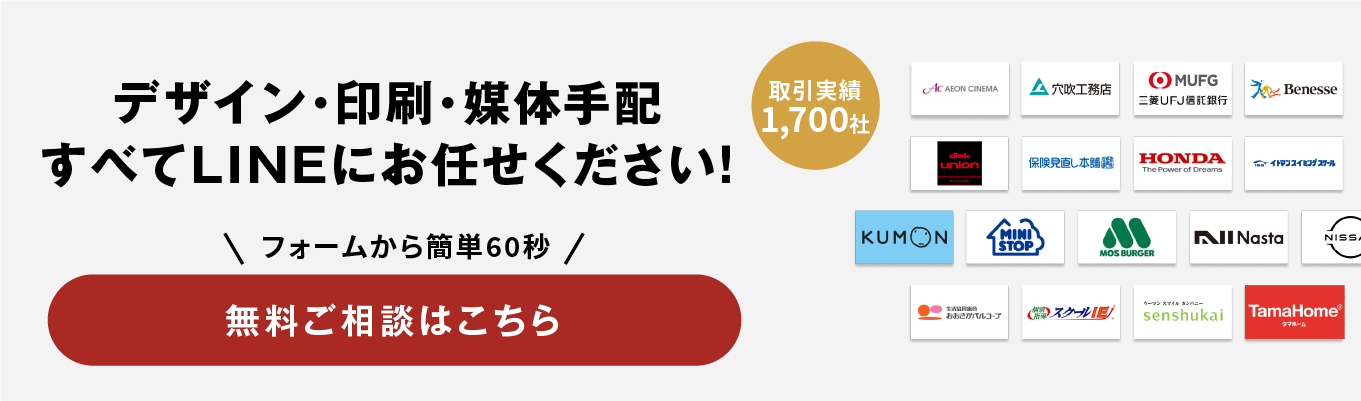
チラシ広告に活用できる助成金・補助金の一覧

チラシ広告の作成には、助成金や補助金を活用できるケースがあります。
チラシ作成にかかわる助成金・補助金の種類には、以下のようなものがあります。
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金
- 商店街復興補助金
- その他自治体独自の補助金
小規模事業者持続化補助金
この補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務改善を目的として行う販促活動に対して支援するもので、チラシの作成や配布費用も補助の対象になります。
2025年からは経営計画の策定に重点を置く方針に変更され、特別枠が整理されました。そのため、従来の「卒業枠」「創業枠」などの特別枠がなくなり、新たに以下の枠が設けられています。
| 枠の種類 | 概要 |
|---|---|
| 通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の 支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みを支援 |
| 賃金引き上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より +30円以上である小規模事業者※赤字事業者は、補助率3/4に引き上げ |
| インボイス特例 | インボイス制度に対応するための経費を支援。チラシ広告費も対象と なる場合あり |
| 災害支援枠 | 災害で被害を受けた事業者が、販路開拓を再開するための経費を補助 |
| 創業型 | 創業間もない事業者向けの支援枠で、新規顧客獲得のための広告宣伝費 などが対象 |
| 共同・協業型 | 複数の事業者が共同で行う販促活動を支援 (地域の商店が合同でチラシを制作する場合など) |
| ビジネスコミュニティ型 | 地域活性化を目的とした事業者グループが利用対象。イベントPRなど チラシ広告に活用可能 |
参照:持続化補助金の概要
それぞれの枠ごとに対象条件が異なり、補助率や上限額も公募のタイミングによって変わるため、申請前に公式サイトで最新情報を確認しましょう。
新事業進出補助金
新事業進出補助金は、2025年に新設された補助金制度です。中小企業や個人事業主が新たな分野への事業展開を行う際に活用できる制度で、チラシ広告を含む販促費用にも利用可能です。
特に、販路開拓や新規顧客の獲得に向けた取り組みとしてチラシを活用する場合、広告費の一部を補助してもらえるため、広告コストを抑えながら効果的なマーケティング活動を展開できる可能性があります。
個人事業主も対象に含まれており、企業規模を問わず申請できる点も大きな魅力です。ただし、現時点では公募回数や申請スケジュールなどの詳細は未定となっているため、最新の情報を中小企業庁の公式サイトなどで確認することが重要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 中小企業や個人事業主が新分野への事業展開を行う際に、必要となる経費 (広告費、設備投資、人材確保等)を支援する補助金制度 |
| 対象者 | 新たな事業に進出する中小企業・小規模事業者・個人事業主 |
| 補助率 | 最大1/2(補助対象経費の2分の1まで補助) |
| 上限額 | 最大1,000万円(事業規模や経費内容により異なる可能性あり) |
商店街振興補助金
商店街振興補助金は、主に各自治体が主体となって実施している補助金制度です。地域の商店街の活性化を目的に、イベント開催費用やPR活動費用、チラシ広告の作成費などを支援するもので、商店街全体または所属する店舗が活用できます。
制度の詳細は自治体ごとに異なり、対象事業者の範囲、補助率、補助上限額、申請時期などは地域によって異なります。そのため、申請を検討する際は、各自治体の公式サイトや窓口で最新の情報を確認することが重要になります。
また、自治体だけでなく、商工会議所や地域の民間団体が独自の支援制度を設けている場合もあります。小規模な補助でも、チラシ広告の作成費用に充てることで、地域密着型の販促活動に活用できる可能性がありますので、商工会議所の公式サイトを確認し、必要に応じてSNSでも最新情報を収集することをおすすめします。
自治体独自の補助金
チラシ広告の作成に活用できる助成金・補助金は、国の制度だけでなく、各自治体が独自に実施しているケースもあります。先述した「商店街振興補助金」以外にも、地域の事業者や店舗の販促・集客支援を目的とした補助制度が多く存在します。
特に自治体が実施する広告宣伝費の支援制度や販路拡大支援事業では、チラシ作成費や印刷費、ポスティング費などが補助対象となることがあります。これらは毎年制度が見直されることも多いため、最新情報は各自治体の公式サイトや広報資料を確認することが大切です。
以下は、過去に実施された自治体独自の補助金制度の一例です。
- 港区広告宣伝活動費支援事業補助金(東京都港区)
- 江東区広告宣伝費補助(東京都江東区)
- 中小企業販路拡大支援事業補助金(福島県南相馬市)
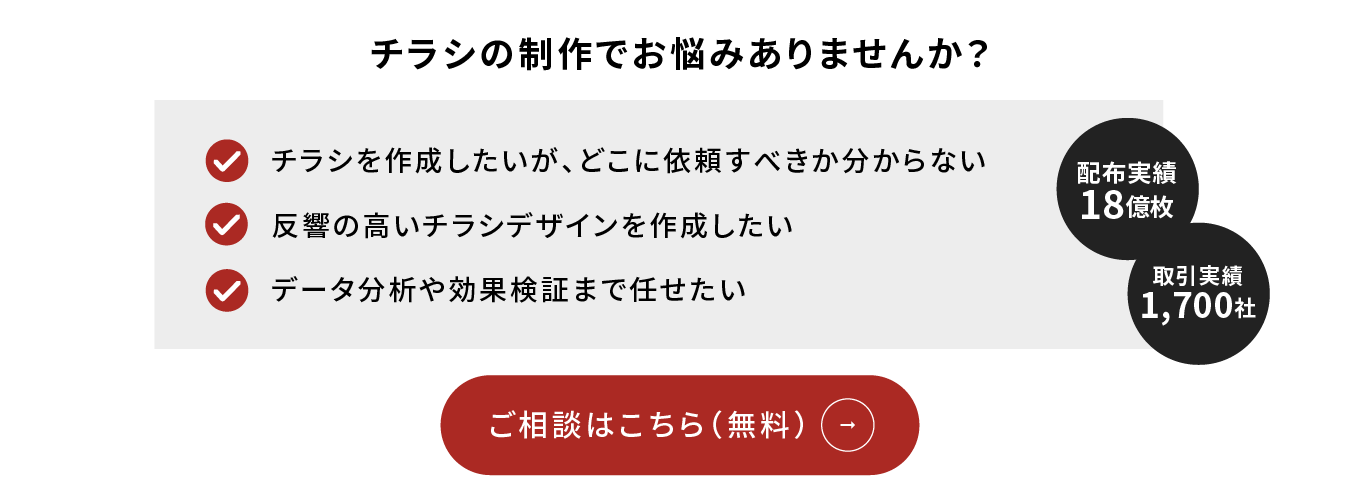
小規模事業者持続化補助金の概要

小規模事業者持続化補助金で抑えておくべき概要は以下の4つです。
- 対象範囲
- 補助率
- 給付を受けるための条件
- 募集期間
上記を理解しておかなければ、適切に助成金や補助金を活用できない可能性があります。特に補助率や募集期間は重要となるため、必ず確認しておきましょう。
対象範囲
小規模事業者持続化補助金を受け取った場合でも、自由に使って良いわけではありません。補助の対象となる主な経費は、以下の表を参考にしてください。
| 補助対象経費科目 | 活用事例 |
|---|---|
| ①機会装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
| ②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
| ⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
| ⑥開発費 | 新商品の施策品開発等に伴う経費 |
| ⑦資料購入費 | 補助事業に関する資料・図書等 |
| ⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
| ⑨借料 | 機会・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
| ⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
| ⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
参照:一般型>ガイドブック
小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は11種類あり、チラシ広告に活用する際には「広報費」に分類されます。尚、2025年からは一部の枠において「車両購入費」や「専門家謝金」なども補助金の対象となっています。
補助率
小規模事業者持続化補助金を受け取れる対象でも、全額を支給してもらえるわけではありません。応募した枠によって上限金額が決まっています。
以下は、2025年度版 小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額をまとめた表です。最新の制度整理により、枠の統合や特例の明確化が行われています。
| 類型 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 2/3 | 50万円 |
| インボイス特例 | 2/3 | 100万円 |
| 賃金引き上げ特例 | 2/3 | 200万円 |
| 災害支援枠 | 2/3 | 200万円 |
| 創業型 | 2/3 | 200万円 |
| 共同・協業型 | 2/3 | 5,000万円 |
| ビジネスコミュニティ型 | 定額 | 100万円 |
参照:持続化補助金の概要
給付を受けるための条件
小規模事業者持続化補助金の給付を受けるための条件は、事業内容や従業員数で定められています。具体的な内容は、以下の表を参考にしてください。
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
|---|---|
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
| 製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
引用元:一般型>ガイドブック
注意点として、小規模事業者持続化補助金の対象となるのは法人や個人事業、特定非営利活動法人のみとなります。また、「共同・協業型」にいたっては、単独申請ではなく複数事業者が協業することが求められます。
株式保有率や課税所得金額によっても左右されるため、事前に要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。
募集期間
小規模事業者持続化補助金は、例年複数回の公募が行われていますが、直近では第16回公募が2024年11月4日に受付を終了しました。2025年2月時点では、次回の公募に関する情報はまだ発表されていません。
例年の傾向から見ると、今後も年に数回のペースで公募が実施される可能性が高いため、チラシ広告の費用支援を検討している方は、公式サイトや商工会議所の情報を定期的に確認しておくことが大切です。
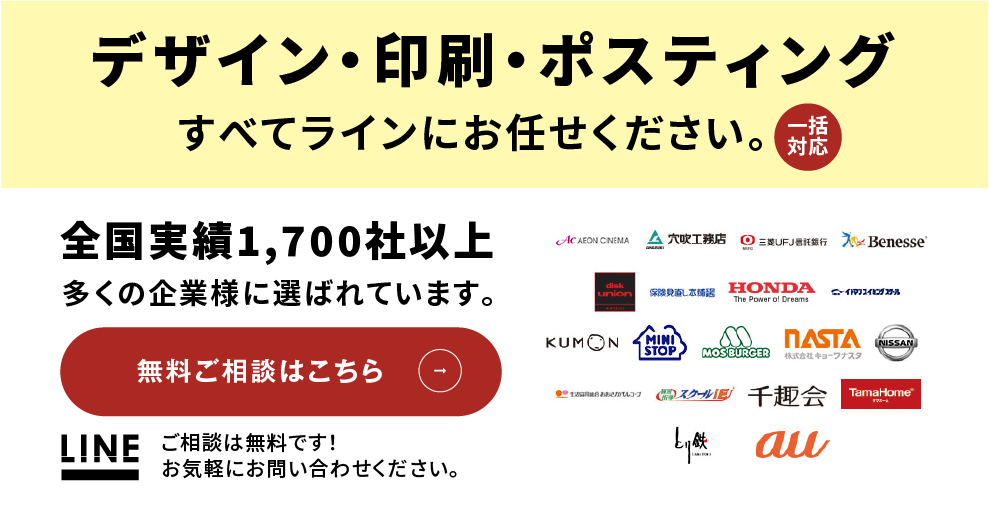
助成金や補助金でチラシ広告を作成するメリット

助成金や補助金でチラシ広告を作成するメリットは以下の3つです。
- チラシ作成にかかる自己負担額を削減できる
- 企業としての社会的信用が上がる
- 雑収入として計上できる
チラシ広告の作成に、助成金や補助金を利用するメリットは資金面だけではありません。社会的信用の側面で考えても、大きなメリットがあることを理解しておきましょう。
チラシ作成にかかる自己負担額を削減できる
助成金や補助金でチラシを作成するメリットは、チラシ作成にかかる自己負担額を削減できることです。国や地方公共団体から補助を受けられれば、本来使用するはずだった会社の資金を別の資金として運用できます。
仮に、銀行や信用金庫から融資を受けた場合、数年かけて利子と一緒に返済する必要があります。助成金や補助金の場合、返済不要なことがほとんどのため安心して利用できます。
個人事業主や中小企業など、広告費に掛けられる予算が少ない場合は助成金や補助金を積極的に活用することをおすすめします。
– 関連記事 –
企業としての社会的信用が上がる
助成金や補助金でチラシを作成するメリットは、企業としての社会的信用が上がることです。助成金や補助金を受けるためには、審査や規制に合格する必要があります。一定の条件を満たして助成金や補助金を受け取った過去があれば、社会からの信用度も上がる可能性があります。
ただし、社会的信用を上げるために申請内容を偽る行為は「不正受給」となるため注意が必要です。不正受給は、企業としての社会的信用を下げてしまう恐れがあることを理解しておきましょう。
雑収入として計上できる
助成金や補助金でチラシを作成するメリットは、雑収入として計上できることです。助成金や補助金は会計帳簿上で「雑収入」として計上します。
例えば、経常利益率が10%の企業の場合、50万円の助成金を受け取れれば500万円の売りがあったのと同様の価値があります。通常の売り上げとして500万円売り上げるのとでは、会社に残る利益に大きな違いがあることを理解しておきましょう。
ただし、消費税の課税対象となるかどうかは補助金の種類によって異なるため、税務処理には注意が必要です。
– 関連記事 –
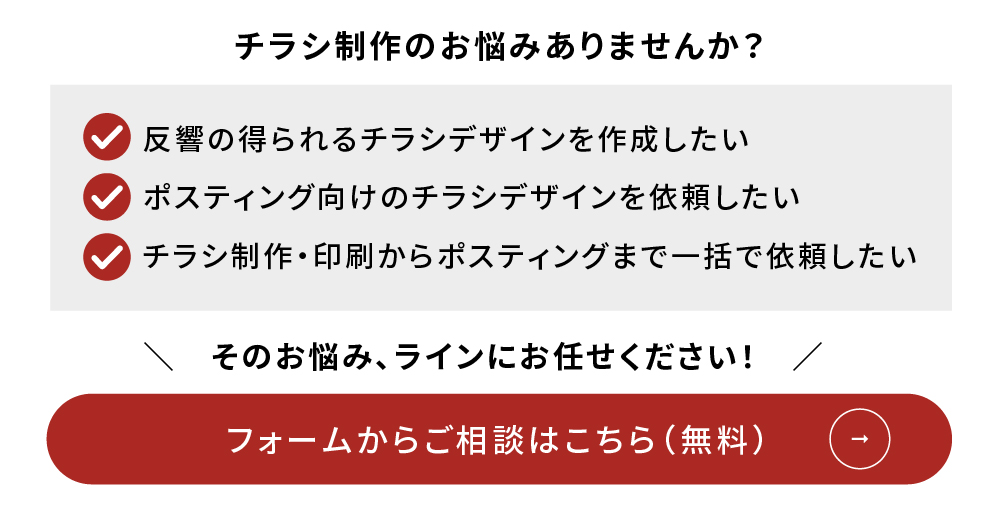
チラシ作成で助成金や補助金を活用する際の注意点

チラシ作成で助成金を活用する際の注意点は以下の5つです。
- 申請スケジュールを事前に確認する
- 対象経費の範囲を確認しておく
- 全額負担ではない点を理解しておく
- 申請から入金までの期間を確認する
- 事後報告や審査に必要な書類を正しく準備する
助成金や補助金の利用で失敗しないためには、利用時の注意点を事前に理解しておく必要があります。キャッシュフローの流れを理解し、計画的にスケジュールを立てましょう。
申請スケジュールを事前に確認する
助成金や補助金を活用してチラシを作成する際は、申請スケジュールを必ず確認しておきましょう。申請期間を過ぎてしまうと、たとえ条件を満たしていても応募できず、次の募集まで数ヶ月待たなければならないケースがあります。
たとえば「小規模事業者持続化補助金」は、年間に複数回の公募が行われる制度ですが、それでも締め切りを逃すと次回の受付まで長期間待つ必要があるため注意が必要です。
また、請には見積書や事業計画書など、複数の書類を準備する必要があり、想像以上に時間と労力がかかることもあります。スケジュールを把握していないと、書類の準備が間に合わず申請自体ができなくなるリスクもあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
対象経費の範囲を確認しておく
補助対象となる経費の範囲を事前に確認することも重要です。一見すると広告費用全体が支援されるように見えても、制度ごとに対象となる経費は異なり、細かく定義されています。
たとえば、同じ広告関連の補助金でも、「販促用のチラシは対象だけど、企業PR目的のチラシは対象外」といったように、用途によって補助の可否が分かれるケースもあります。このようなルールに気づかず申請してしまうと、あとで経費が認められず自己負担になる可能性もあるため注意が必要です。
具体例としては、高知市が実施している「販路拡大サポート事業」があります。この制度では、「広告媒体への掲載料は補助対象」ですが、「チラシなどのデザイン費用は対象外」とされています。このように、一部の工程や費用だけが対象になる補助制度も少なくないため、制度ごとのガイドラインを必ず確認してましょう。
全額負担ではない点を理解しておく
助成金や補助金を活用する際の注意点として、全額負担ではないことにも注意が必要です。多くの助成金や補助金は、全額を負担してくれる制度ではありません。どの程度補助を受けられるのかを理解せずに経営を進めると、補助を受ける前に資金が足りなくなる恐れがあります。
さらに、助成金や補助金を受け取るために取り組みを行う際にも注意が必要となります。条件に合うように正社員雇用や研修制度を新設することで、新たな費用がかかる可能性があります。結果的に、資金繰りが厳しくなる恐れもあるため注意が必要です。
申請から入金までの期間を確認する
助成金や補助金を活用する際には、申請から入金までの期間も確認しておきましょう。助成金や補助金は、事業を実施した後に支払われるのが一般的です。そのため、前払いだと勘違いして申請してしまうと、途中で資金繰りがうまくいかない恐れがあります。
いつ入金されるかを事前に確認しておき、入金までに必要な資金も必ず用意しておきましょう。
事後報告や審査に必要な書類を正しく準備する
助成金や補助金の支給を受けるためには、申請するだけではなく、事後報告や審査の際に必要となる書類を正しく準備し、期限内に提出する必要があります。
書類が不備だったり、提出が遅れた場合には、助成金・補助金を受け取れない可能性があるため、注意が必要です。
制度によって細かい書類内容は異なりますが、チラシ制作に関わる助成金・補助金で主に求められる書類には、以下のようなものがあります。
- 実績報告書
- 収支報告書
- 活動資料(実施報告など)
- 外部業者委託時の契約書・発注書
- チラシの現物やPDFデータ
これらの書類は、事後提出の締切が設けられていることが一般的です。提出期限を過ぎてしまうと申請が無効になることもあるため、制作スケジュールだけでなく、報告のスケジュールも含めて逆算して準備しておくことをおすすめします。
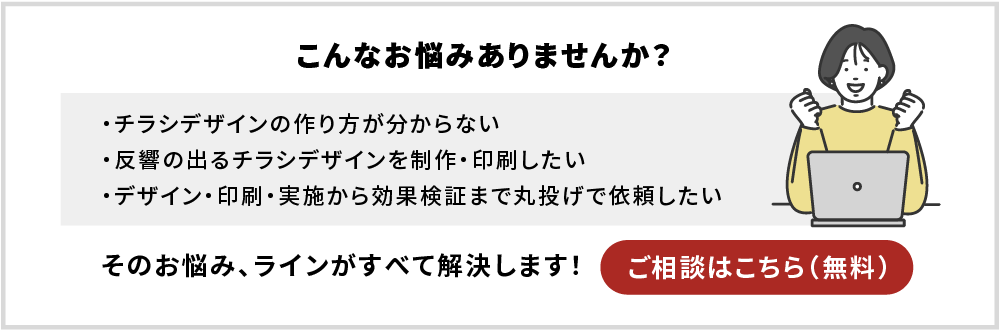
チラシのデザイン作成・印刷の依頼は株式会社ラインへ

助成金や補助金を有効活用して使える資金を増やすことで、チラシの作成費を抑えることが可能です。また、助成金や補助金で得られた資金を適切にチラシ作成に使用することも大切です。
チラシの活用を検討している場合は、株式会社ラインにご相談ください。株式会社ラインでは、幅広いジャンルやエリアでのチラシ作成やポスティングの実績があります。得た資金を無駄にしないためにも、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
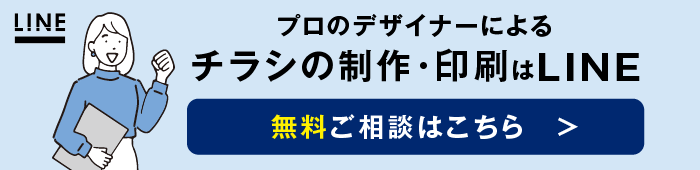
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 26年02月04日
26年02月04日