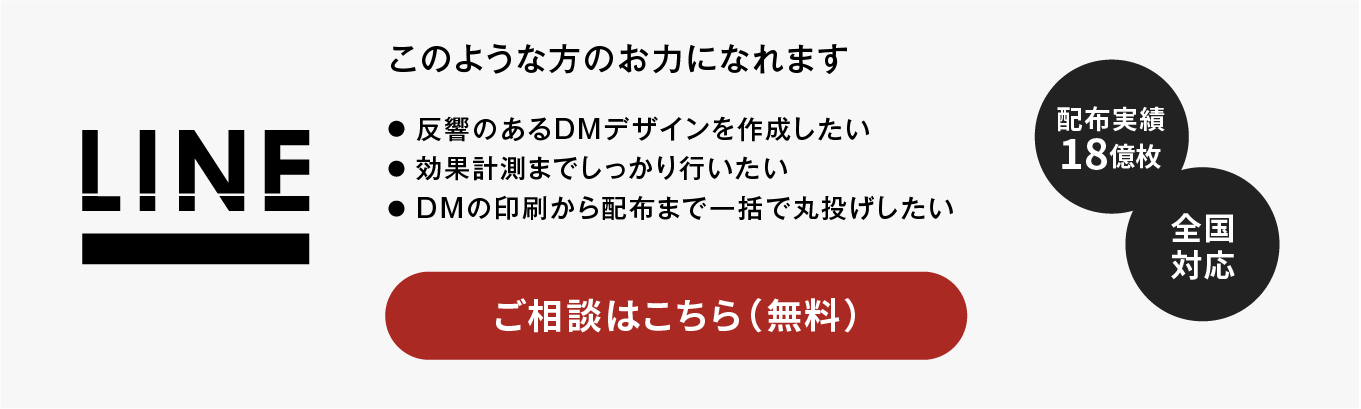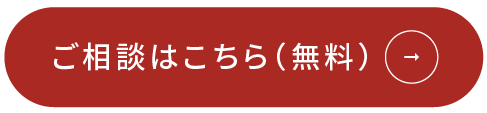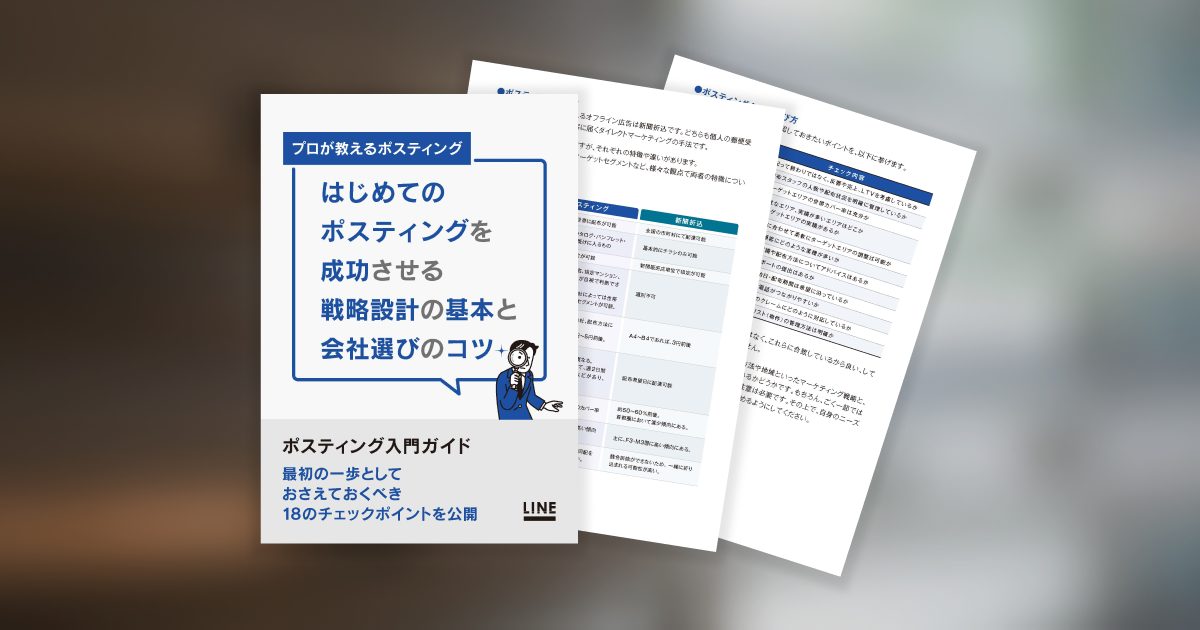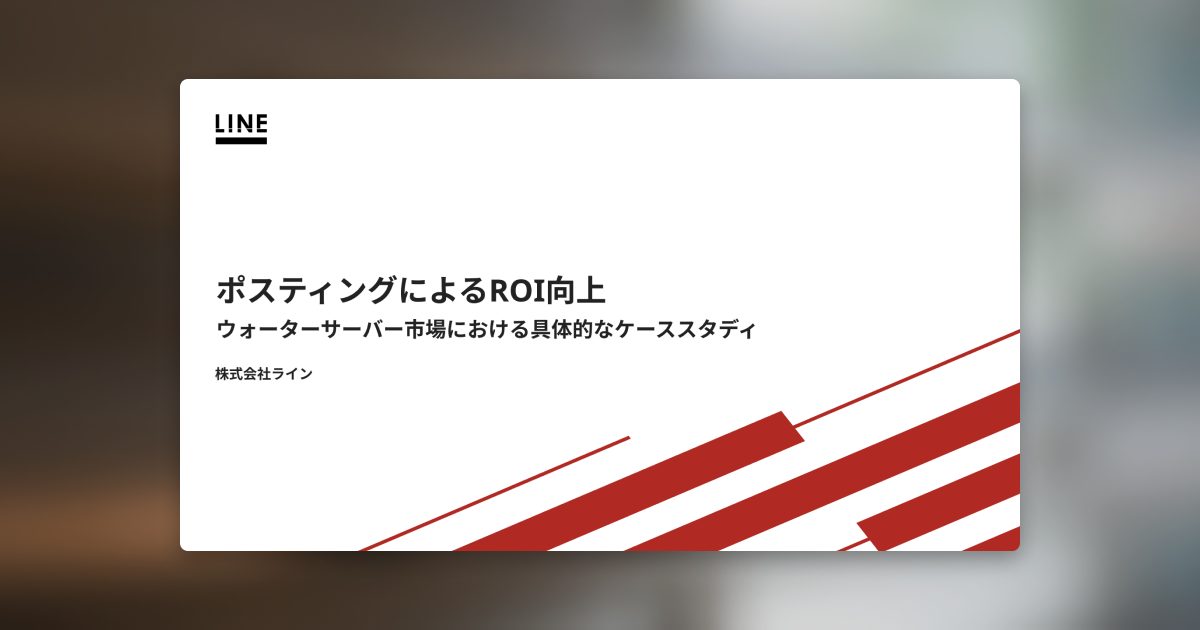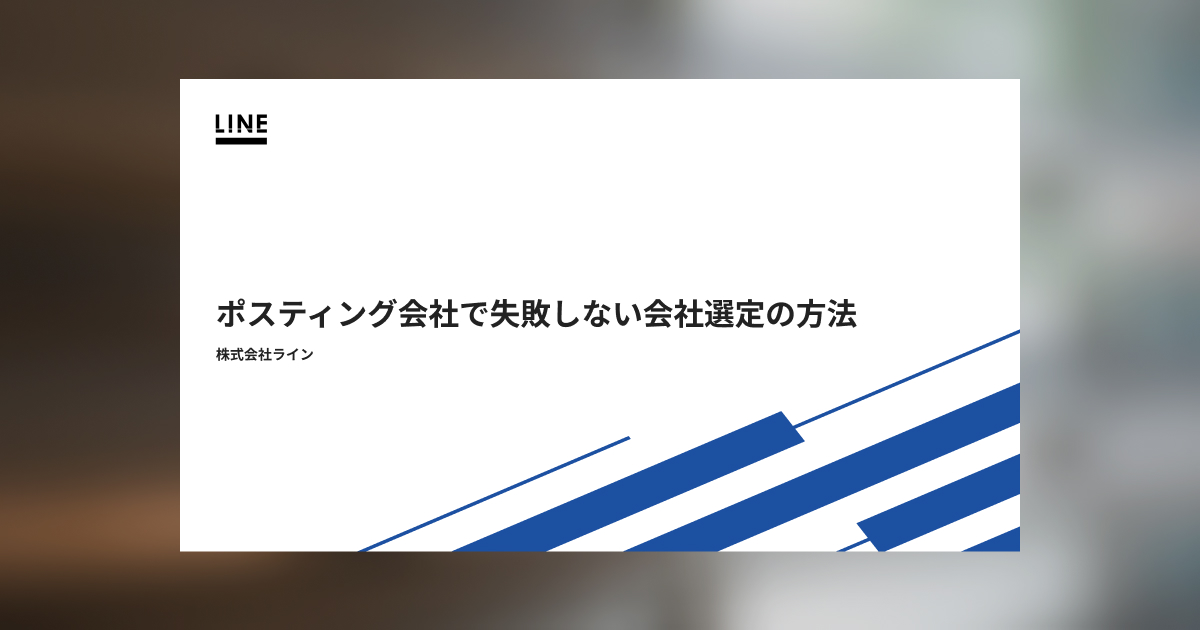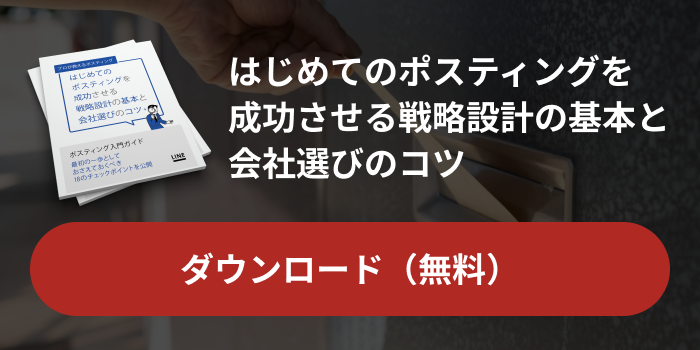DM(ダイレクトメール)の種類は?それぞれの特徴や活用すべきケースを紹介
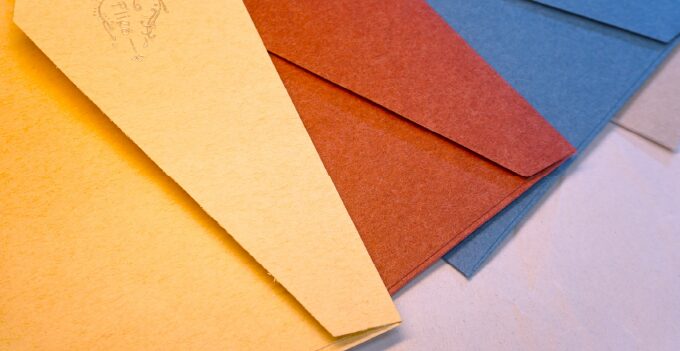
商材の宣伝活動として活用されることが多い「DM(ダイレクトメール)」。DMといっても様々な種類があり、種類によって特徴や活用すべきケースは異なります。自社の商材や目的に合わせて適切なDMを活用することができれば、DMの効果を最大化できる可能性があります。
本記事ではは、DMの種類や種類別の特徴、活用すべきケースについて解説します。この記事を参考に、適切なDM選びのコツを理解しましょう。
目次
DM(ダイレクトメール)とは?

DM (ダイレクトメール)とは、宣伝を目的として特定のターゲットに送られる、電子メールやハガキなどの印刷物のことです。
DMは不特定多数に宣伝できる広告手法とは異なり、拡散力がやや劣りますが、特定のターゲットに対して宣伝することにより、興味を惹きやすくなるメリットがあります。興味を惹くことができれば、購入や問い合わせに繋げることも可能です。
また、特定のターゲットに宣伝する効率的な方法であるだけでなく、より成約に繋げやすい可能性もあることから、DMを活用した方が良いケースが多くあります。
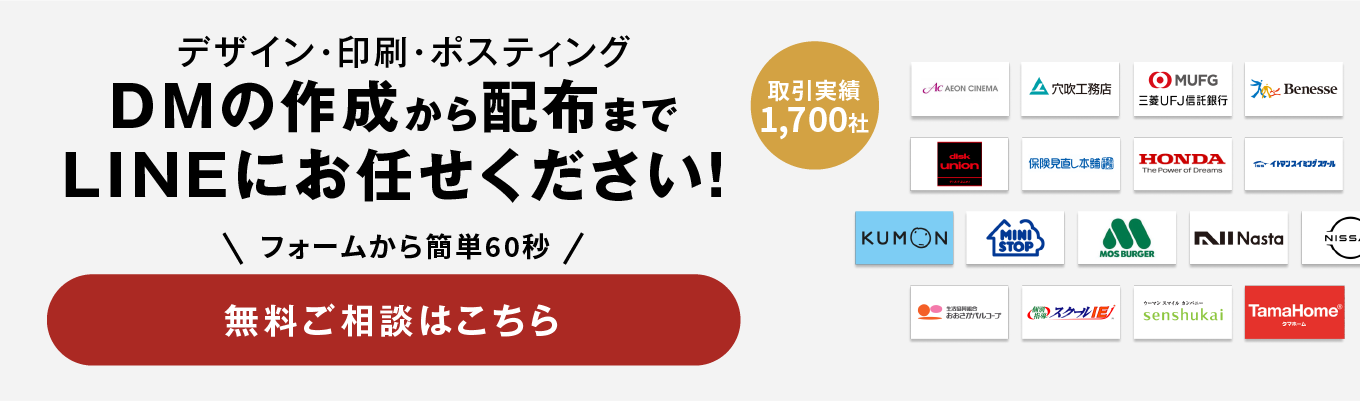
【送り方別】DM(ダイレクトメール)の種類
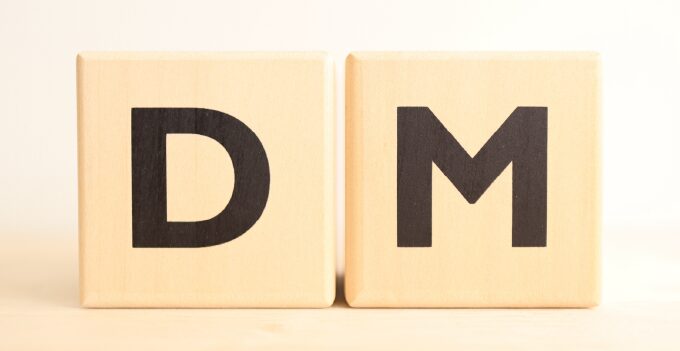
ダイレクトメール(DM)は、目的やターゲットに合わせてさまざまな手法があります。ここでは、送り方別に、以下の4つの特徴と活用すべきケースをご紹介します。
- DMハガキ
- 封筒DM
- 電子DM
- FAXDM
- サンプリングDM
宣伝目的やターゲットへの訴求内容によって、適切なDMの種類は異なります。それぞれの特徴だけでなく、メリットやデメリットも理解した上で適切なものを選択しましょう。
DMハガキの特徴
DMハガキは、はがきサイズで届けるシンプルなダイレクトメールです。1枚で伝えたい情報を端的に届けることができるため、低コストかつ手軽に送付できます。
近年では、インターネットが普及したことで、紙媒体を選択しない企業も増加傾向にありますが、インターネット広告よりもすぐに始められ、直接手にとってもらえる機会が高いことから、DMハガキを活用した方が良いケースがあります。
DMハガキのメリット・デメリット
DMハガキのメリット・デメリットは、以下の表を参考にしてください。
| ハガキのメリット | ハガキのデメリット |
|---|---|
| DMの中でも比較的コストを抑えやすい | サイズが小さく情報量に限界がある |
| 圧着ハガキは情報をコンパクトに伝えられる | 開封しなければ内容を確認できないものがある |
| 直接手に取って見てもらえる可能性が高い | 目立たないと他の郵便物に埋もれてしまう |
ハガキによるDMは、他のDMよりも比較的コストを抑えられることが特徴です。両面が接着されている圧着ハガキを活用すれば、配送費を抑えつつ掲載できる情報量を増やせます。
ただし、開封しなければ内容を確認できないため、関係ないと思われてしまうと開封する前に捨てられてしまう恐れもあるため注意が必要です。
– 関連記事 –
ハガキを活用すべきケース
DMハガキを活用すべきケースは、自社商材の宣伝やイベントを開催するときです。拡散力はそれほど高くはありませんが、特定のターゲットに対して商材に対する興味を惹きやすいため、成約に繋げやすくなります。
また、ハガキにキャンペーン情報や割引クーポンをつけることで、さらに成約率を高められる可能性があります。
封筒DMの特徴
DMには封筒を用いた宣伝方法もあり、封筒を活用することで他のDMとも差別化が図れます。また、封筒のサイズや素材、色を変更することで、ターゲットに対して様々な印象を与えられます。
封筒DMは、圧着ハガキと同様に開封するまで中身が分からないため、興味を惹けなければ開封されないデメリットもありますが、内容がわからない分、中身に興味をもってもらえる可能性もあります。
封筒のメリット・デメリット
封筒のメリット・デメリットは、以下の表を参考にしてください。
| 封筒のメリット | 封筒のデメリット |
|---|---|
| ターゲットごとに適切な情報を選択できる | 開封するまで中身がわからない |
| 多くの情報を訴求できる | 作成に時間や費用がかかる |
| 封筒により特別感や信頼感を演出できる | DMはがきに比べてコストが高い |
封筒を活用する最大のメリットは、ターゲットに合わせて情報を変えられることです。封筒の内容を変えるだけでなく、中身を自由に増減できるため、一度に多くの情報を伝えられます。クーポン券や割引券などを同封すれば、成約に繋げやすくなるのもメリットです。
ただし、ターゲットに合わせて内容を変更しなければいけないため、作成するのに時間や費用がかかる可能性があります。
開封するまで中身がわからないデメリットもありますが、OPP袋を活用するのもおすすめです。OPP袋とは、プラスチック素材の透明のフィルムのことで、封筒が雨で濡れてしまうことも防げます。中身も開封せずにわかるため、封筒のデメリットを減らしつつ、メリットを生かすことが可能です。
封筒を活用すべきケース
封筒を活用すべきケースは、一度に大量の販促物を送りたい場合です。チラシやハガキを分けて大量に送付してしまうと受け取り手に何度も手間をかけてしまう可能性があります。
封筒でまとめて郵送することができれば、かさばることなく、情報が整理されていてターゲットにも内容を伝えやすくなります。新たな商材やサービスを展開した際には、封筒を活用してまとめて送付することをおすすめします。
電子DMの特徴
電子DMとは、電子メールやSNSのメッセージ機能を活用して届けるデジタル型のダイレクトメールです。紙媒体を活用したDMとは異なり、印刷コストがかからないため費用を抑えられるのが特徴です。
ただし、ターゲットの連絡先がなければ直接DMを送付することができません。たとえDMが送れたとしても、数多くのメールに埋もれてしまう可能性もあり、期待する反響率を得られない恐れがあります。
電子DMのメリット・デメリット
電子DMのメリット・デメリットは、以下の表を参考にしてください。
| 電子DMのメリット | 電子DMのデメリット |
|---|---|
| 情報量に制限がない | 商材によっては相性が良くない |
| 費用が抑えられる | メールアドレスを取得していないと送れない |
| 複数のターゲットに効率的に訴求できる | 他の電子メールに埋もれてしまう可能性がある |
| 開封率やクリック率をデータで計測できる | 迷惑メールとしてブロックされるリスクがある |
電子DMでは、紙媒体のように掲載できる情報量に制限がありません。そのため、伝えたい情報を全て伝えることが可能です。また、複数のターゲットに同時にアプローチできるため、効率が良い側面もあります。反響数も他の宣伝方法よりも測りやすいため、効果測定を行いやすいのもメリットです。
ただし、商材によっては紙媒体の方が相性が良い場合もあります。さらに、メールアドレスを知らなければ電子DMを送付できません。近年ではSNSも普及しているため、連絡先を知らない場合にはSNSのダイレクトメッセージ機能を活用することをおすすめします。
電子DMを活用すべきケース
大量の情報を効率的に送付したいときには、電子DMを活用しましょう。電子DMには一斉送信できる機能があるため効率的に訴求が可能です。
また、紙媒体のようにチラシ制作、印刷などの手間がかからないため、人材が不足しているときの広告手法としてもおすすめです。
FAXDMの特徴
FAXDMとは、FAXを活用してDMを送付する方法です。FAXを活用するため、配布が簡単なだけでなく、常に最新の情報を訴求できるのが大きなメリットです。
また、家庭によっては現在でもFAXを活用していることがあるため、特定の家庭や企業に訴求しやすい方法として挙げられます。
FAXDMのメリット・デメリット
FAXDMのメリット・デメリットは、以下の表を参考にしてください。
| FAXDMのメリット | FAXDMのデメリット |
|---|---|
| 自宅や企業に届くため目に留まりやすい | 紙やインクの消費でクレームに繋がる恐れがある |
| 紙で届くため閲覧率が高い | カラーでの配布がしづらい |
| FAXを活用している年齢層に訴求しやすい | 個人向けに訴求しづらい |
FAXDMは、紙で届くため、目に留まりやすい点が強みです。また、すぐに顧客に情報を訴求でき、配布の労力を削減することも可能です。比較的高齢の世帯で家庭用にFAXを活用しているケースがあるため、一定の年齢層に訴求しやすいのもメリットです。
FAXDMのデメリットとしては、FAXを配布することによって、受け取り先の紙やインクが消費されることが挙げられます。そのため、商材に興味の無い顧客からは、紙やインクを無駄に消費したことを理由にクレームに繋がる恐れがあることを理解しておきましょう。
FAXDMを活用すべきケース
FAXDMは、簡単に紙で送付できるのが最大のメリットです。そのため、ポスティングや郵送のように時間や手間をかけず、紙を活用したDM配布を行いたい場合におすすめです。
また、配布に時間や手間がかからないため、広告出稿の中でも人員を削減しながらできる方法となります。
サンプリングDMの特徴
サンプリングDMは、商品や試供品を実際に同封して送付するダイレクトメールです。受け取った人に直接商品を試してもらえるため、紙面だけでは伝わらない魅力をダイレクトに届けられます。
特に香りや味、肌ざわりといった体験価値を伝える商材との相性が良く、購買意欲の喚起に直結しやすい点が大きな特徴です。リアルな体験をきっかけに、その後の購入や資料請求につながるケースも多く、販促効果の高い手法として注目されています。
FAXDMのメリット・デメリット
FAXDMのメリット・デメリットは、以下の表を参考にしてください。
| サンプリングDMのメリット | サンプリングDMのデメリット |
|---|---|
| 商品の使用感や品質をダイレクトに伝えられる | 郵送コスト・制作費が高くなりやすい |
| 記憶に残りやすい | 物流や梱包の手間がかかる |
| 資料請求や購買など具体的な行動に結びつきやすい | ターゲティングの精度が求められる |
サンプリングDMは、実際に商品を手に取って試してもらえるため、紙面だけでは伝わりにくい品質や使用感をリアルに届けられるのが大きなメリットです。体験を通じて強い印象を残せるため購買や資料請求などの具体的な行動につながりやすく、DMの反応率向上も期待できます。
一方で、サンプル制作や梱包、発送にかかるコストが高くなりやすい点はデメリットです。興味の薄い層に送付すると費用に見合う効果が得られにくいため、精度の高いターゲティングや配布件数の管理が重要になります。
サンプリングDMを活用すべきケース
サンプリングDMは、化粧品・香水・健康食品・飲料など、実際に使ってみることで価値が伝わる商品に特におすすめです。既存のロイヤル顧客に向けた先行配布として使えば、ブランドへの愛着をさらに深める効果も期待できます。
また、アンケートやレビューの収集を組み合わせることで、リアルな声を集めながら商品改善や口コミ拡散にもつなげられます。
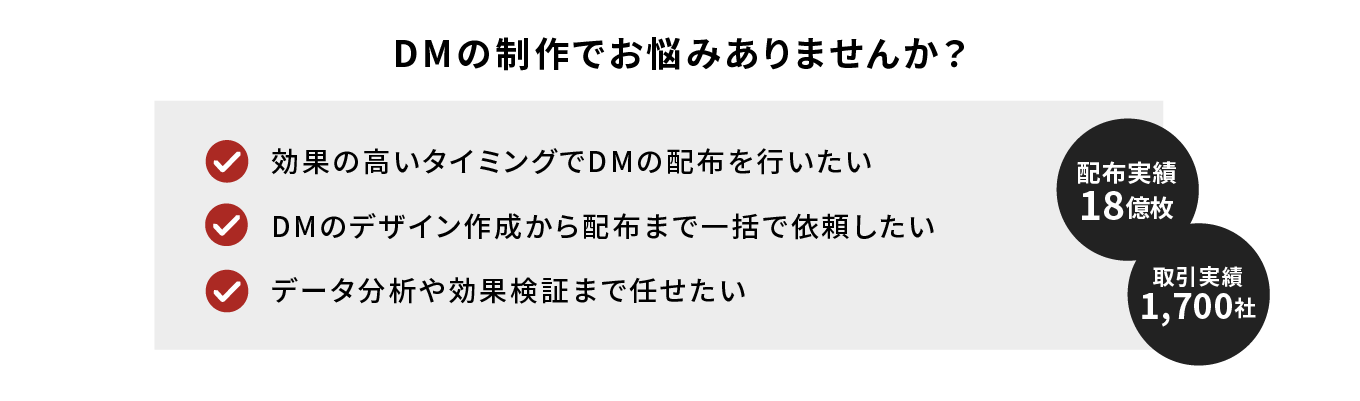
【用途別】おすすめのDMサイズの種類

DMは「誰に・何を・どのように届けたいか」という目的によって、最適なサイズを選ぶことが重要です。サイズによって郵送コストや伝わり方、受け手の印象が大きく変わるため、期待する効果に合わせて適切に選定しましょう。
代表的なDMサイズとその活用シーンを以下で詳しくご紹介します。
通常はがきサイズ|コストを抑えて既存顧客に手軽に知らせたいときに
通常はがきサイズ(100mm×148mm)は、官製はがきと同じサイズで郵送コストが抑えられる点が魅力です。シンプルに情報を伝えられ、封筒を開けなくても内容を一目で確認してもらえるメリットがあります。
特に会員向けの通知や定期的なキャンペーン案内など、手軽にアプローチしたいケースに適しており、小ロットでの配布や継続的な施策にも向いています。
コストパフォーマンスを重視しながら確実に情報を届けたいときにおすすめです。
長形3号サイズ|新商品やキャンペーンを印象づけたいときに
長形3号サイズ(120mm×235mm)は定形郵便の最大サイズで、通常のはがきよりもインパクトがあります。他の郵便物と並んだときに目を引きやすく、自然と手に取ってもらえるのが大きな強みです。
デザイン性の高い紙面と相性が良く、新商品やキャンペーンの訴求に適しています。さらにビジネス書類やクーポン券の挿入もしやすく、目立つことが重要なDM施策で特に効果が期待できます。
A4サイズ|情報量が多く商材の魅力をしっかり伝えたいときに
A4サイズ(210mm×297mm)は大判で視認性に優れ、文字情報・写真・図解など豊富な情報を盛り込めます。特に新規顧客向けに、サービス内容やキャンペーンを詳しく説明したいときに適しています。
さらに圧着タイプにすれば、情報量を増やしつつ開封率も高められます。高単価商材の提案や法人営業、信頼性を重視するDMとして活用しやすく、安心感と説得力を同時に伝えたい場合におすすめです。
A4サイズ(OPP封筒)|チラシを封入して特典感や演出を高めたいときに
A4サイズのチラシを透明フィルム(OPP封筒)に封入して届ける方法は、汚れや水濡れを防ぎながらしっかりと情報を保護できるのがメリットです。
また、中身が見えることで特典やセール情報の「お得感」を演出でき、受け取った側に安心感を与えやすいのも魅力です。
キャンペーン案内や優待の通知など、個人宛に特別感を出したいときに最適で、チラシを差し替えるだけで内容の変更がしやすい点も活用しやすいポイントです。
A5サイズ|イベント案内やプロモーション情報をしっかり伝えたいときに
A5サイズ(148mm×210mm)は、持ち運びやすく手に取りやすいサイズ感でありながら、十分な情報量を掲載できる点が魅力です。
一般的な郵便物よりもひとまわり大きく目立ちやすいため、イベント告知やプロモーション情報のDMにおすすめです。写真や図版を効果的に使うことで視覚的インパクトも演出でき、配布後の反響を高めたいときにおすすめです。
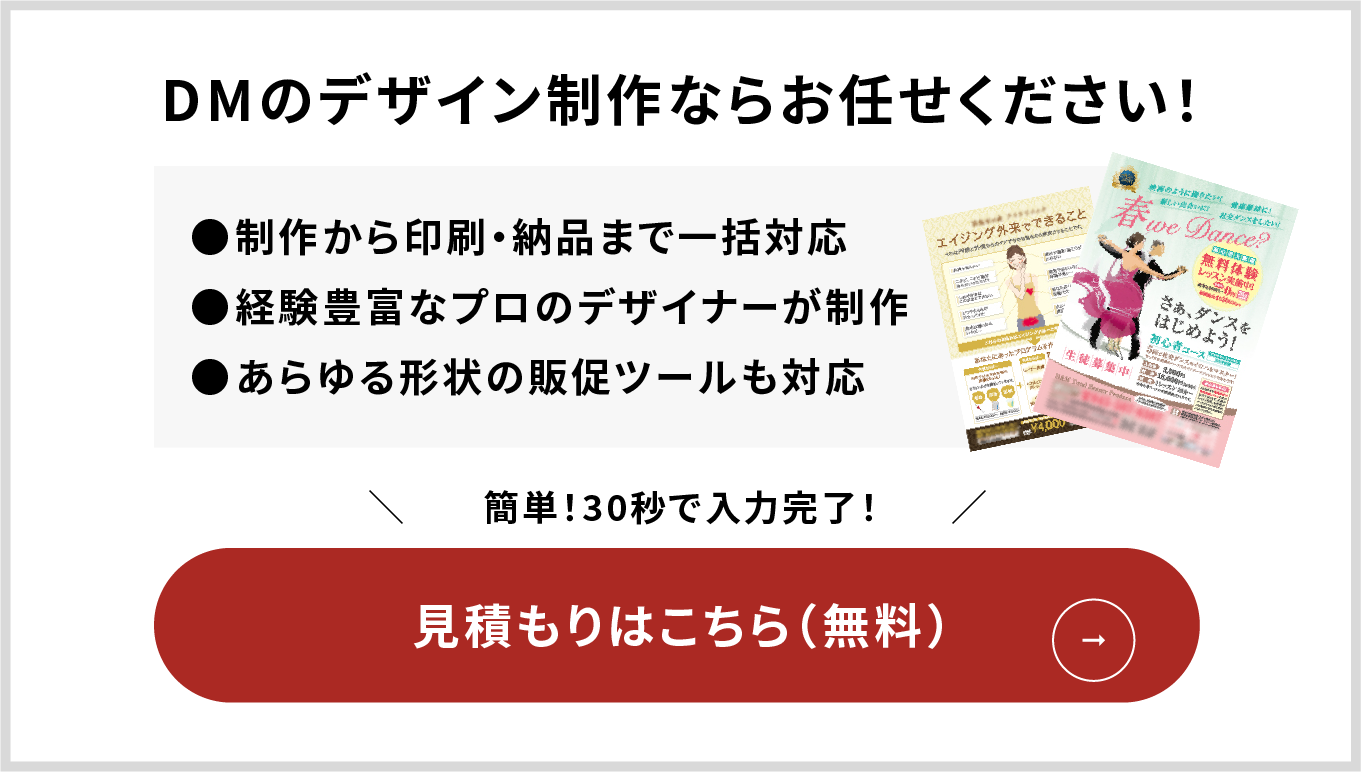
DMの種類とサイズを選ぶポイント3つ

DMのサイズや種類を「なんとなく」で決めてしまうと、訴求力や費用対効果を十分に発揮できない場合があります。届けたい相手や目的に合わせて、最適なDMの形を選ぶことが大切です。
ここでは、DMの種類とサイズを選ぶ際に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
- ターゲットや目的|「誰に・何をしてほしいか」を明確にする
- 情報量|伝えたい内容と可読性のバランスに注意する
- 費用|印刷・郵送費を含めたコストを考慮する
1.ターゲットや目的|「誰に・何をしてほしいか」を明確にする
DMの種類・サイズ選びは「誰に」「何をしてほしいのか」から逆算するのが基本です。ターゲットの年齢層や興味関心によって反応しやすいDMの形式は異なります。
例えば高齢者層には文字が大きく読みやすい大判DMやA4サイズが向いており、ビジネス層には情報を整理したA4封筒DMに効果が期待できます。
さらに、目的別におすすめのサイズを以下のように整理できます。
- 再来店・リピート促進:圧着はがきDM
- 新規獲得・ブランド訴求:大判はがき、A4封筒DM
- 資料請求・問い合わせ:A4封筒DM
- CV促進:サンプルDM
このように、「誰に・何を・どう伝えるか」が明確になるほど、選ぶべきDMの種類とサイズが見えてきます。
2.情報量|伝えたい内容と可読性のバランスに注意する
DMで伝えたい情報量と可読性のバランスを考えることも重要です。伝えたい内容が多い場合には、大きめのサイズや折り加工を取り入れることで見やすく整理できます。
一方、短いメッセージで十分なケースでは、はがきサイズでコンパクトに届ける方が受け手の負担が少なく効果が期待できます。
ただし、高齢者層には、小さな文字が読みづらいことがあるため、情報量が少なくても大きめのサイズを選ぶと安心です。圧着DMを活用すれば、サイズを抑えながら情報量を増やすこともできます。
このように、伝えたい内容量と相手が読みやすい形式のバランスをとることが大切です。
3.費用|印刷・郵送費を含めたコストを考慮する
DMの制作ではデザイン費だけでなく、印刷費や郵送費などトータルのコストを把握しておくことが大切です。
例えば、A4封筒DMは信頼感や情報量の多さで優れる一方、封入作業や定形外郵便の送料などでコストがかさみやすいです。反対に通常はがきサイズなら定形郵便で送料を抑えつつ大量配布の場合に適しています。
また、ターゲットの数や配布頻度、想定される反応率なども含めて、総合的な費用対効果を計算して最適なDM形式を選択することが重要になります。
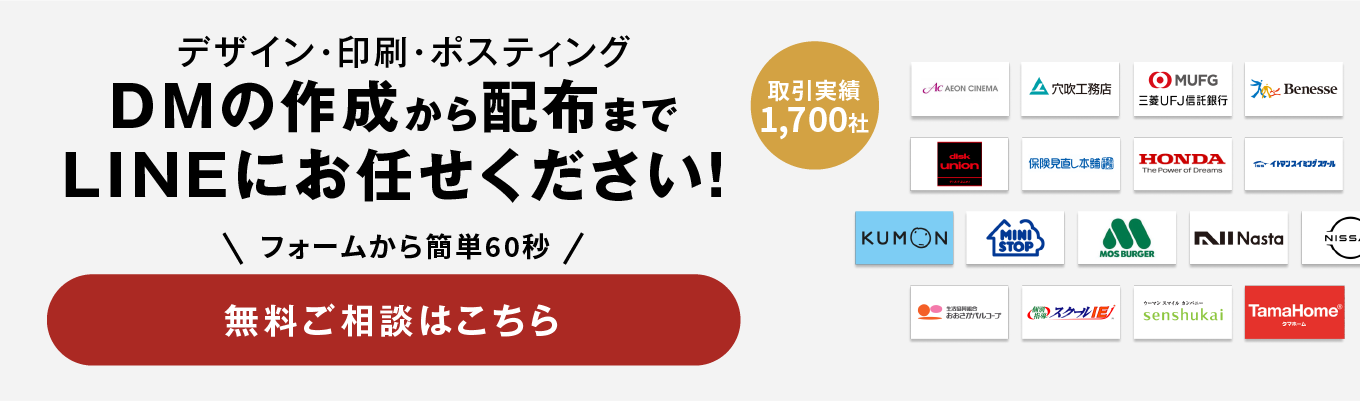
DMにおける開封率と反響率の違い

DMを活用する際には、開封率と反響率の違いについて理解しておくことが大切です。開封率と反響率の違いは、下記を参考にしてください。
- 開封率:送付したDMが開封された割合のこと
- 反響率:送付したDMに対する反響の割合のこと
例えば、開封率が高くても反響率が低ければ、最終的な成約には繋がりません。開封率が低い場合には、ターゲット層やDMの内容で興味を惹けてない可能性が考えられます。
DMを活用する際には、開封率と反響率の違いについて理解した上で、数値の変化によって適切な対策を立てることが重要です。対策によって数値が変化した際に「なぜ数値が変わったのか」を考えることで、次の戦略にも生かしやすくなります。
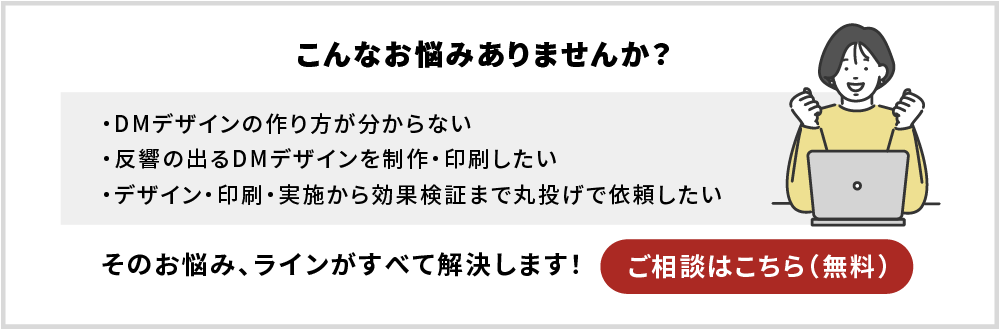
DM(ダイレクトメール)の反響率を高めるには?

DM(ダイレクトメール)の反響率を高める方法は、以下の5つが挙げられます。
- 明確な目的・ターゲット設定を行う
- 費用対効果を分析する
- 配布するタイミングを精査する
- ターゲットに合わせてDMのデザインや内容を変更する
- DMの専門会社に依頼する
これらの方法を組み合わせることで、よりDMの反響率を高められる可能性があります。
明確な目的・ターゲット設定を行う
DMの反響率を高めるためには、明確な目的・ターゲット設定を行うことが大切です。目的やターゲット設定が明確にされていなければ、DMを見てもらうことができない可能性があります。
例えば、思いつきで30代の男女にDMを送信した場合と、35歳によくある肌トラブルで悩んでいる人に対してDMを送った場合では、反響率に大きな差が出る可能性が高いです。
また、目的やターゲット設定が明確になっていなければ、DMを送る数や内容が絞りきれず無駄にコストがかかってしまう恐れもあります。DMの反響率をより高められるよう事前に明確な目的・ターゲット設定をしっかりと行いましょう。
費用対効果を分析する
費用対効果を分析することも、DMの反響率を高めるために重要です。DMやチラシのような宣伝活動を行う場合、反響数や売上げにばかり気を取られてしまうかもしれませんが、反響数が多くても、費用や手間を大幅にかけたことによって、費用対効果が下がっていれば赤字となる可能性があります。
最終的な売り上げや反響数だけに注目するのではなく、費用対効果を分析した上で反響率を高めましょう。
– 関連記事 –
配布するタイミングを精査する
DMの反響率を高めるためには、配布するタイミングにも注目しましょう。特におすすめのタイミングとしては、商材の買い替えやシーズンの変わり目などが挙げられます。過去の顧客の傾向から、購入履歴に合わせて最適なタイミングでDMを配布することで、高い反響を得やすくなります。
また、配布する方法も重要です。DMをポスティングで配布するのか、直接手渡しするのかによっても、配布後の反響率に差が出ることがあるため、様々な配布方法でどのタイミングに配布すると反響率が高いのかを試してみることをおすすめします。
ターゲットに合わせてDMのデザインや内容を変更する
DMの反響率を高めるためには、ターゲットに合わせてデザインや内容を変更することをおすすめします。DMのデザインや内容によって、反響率は大きく変わります。
例えば、サイズが小さくても、少しの情報量でキャンペーンなどを掲載できるハガキは、新規顧客の集客におすすめです。
反対に、すでに自社商材に興味のある既存顧客に配布する際には、大きめのサイズで情報量も多く掲載したDMの方が高い効果を得られる可能性があります。
このように、ターゲットに合わせてデザインや内容を変更することで、反響率を高めやすくなります。
DMの専門会社に依頼する
DMの専門会社に依頼することも、反響率を高めるための手段としておすすめです。DMには多くの種類があり、特徴やメリット・デメリットだけでなく、自社の商材と相性が良いかも判断しなければなりません。
さらに、開封率や反響率を調べた上で効果測定を繰り返しながら徐々に数値を高めていくことが大切です。
通常業務をこなしながら、DMにかける手間や時間を確保できない場合も多く、どちらかが中途半端になってしまっては意味がありません。
DMの専門会社へ依頼すれば、最適なDMの種類を選択してもらえるなど、要望に合わせてさまざまな提案をしてもらえます。手間や時間を大幅に削減した上で、プロのノウハウをもとに効果的な宣伝が可能になります。
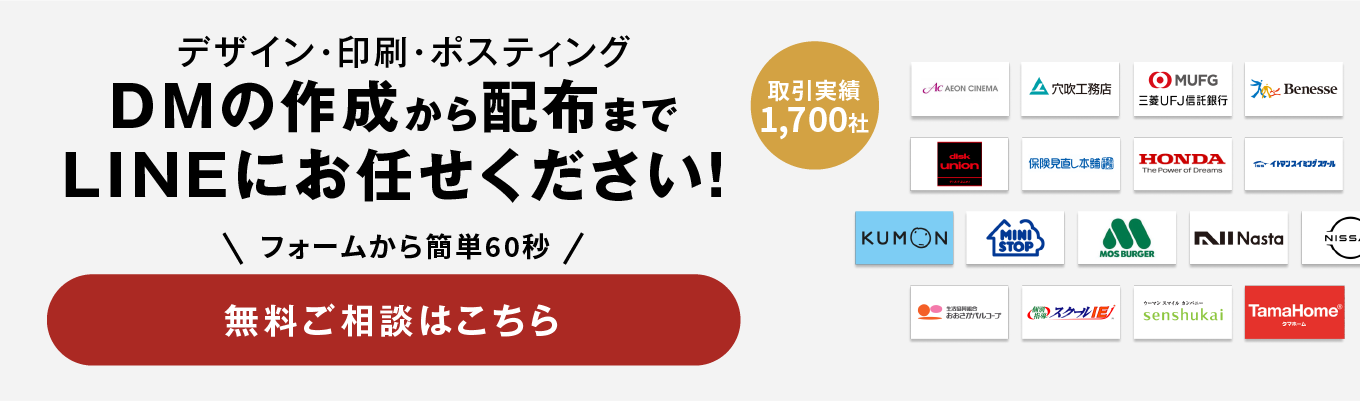
DMの種類によって活用するケースを変えよう

DMの集客効果を最大化するためには、DMの種類によって活用するケースを変えることが大切です。同じ手間やコストをかけたとしても、DMの種類や商材、ターゲットがマッチしていないだけで、効果が大きく変わってしまう可能性があります。
DMを活用して宣伝活動をしたいと考えているなら、株式会社ラインへご相談ください。株式会社ラインでは、 経験豊富なデザイナーがターゲットに合わせたDMを作成いたします。
また、結果を検証しながら、継続的な改善もご依頼いただけるため、ぜひ一度株式会社ラインへお気軽にお問い合わせください。
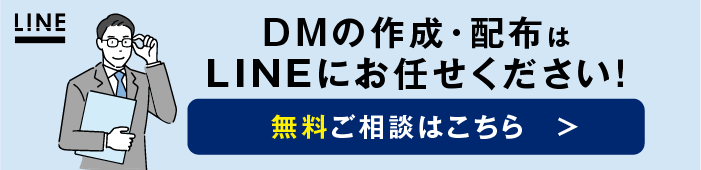
全国47都道府県でポスティング対応可能
この記事を書いた人

ライン編集部

ライン編集部

 26年02月04日
26年02月04日